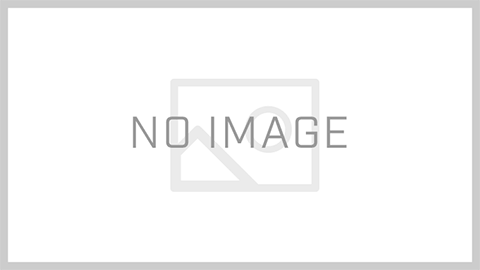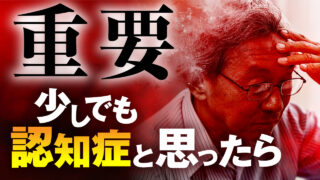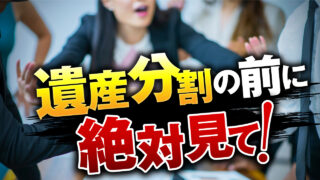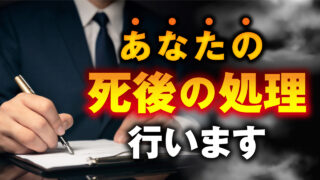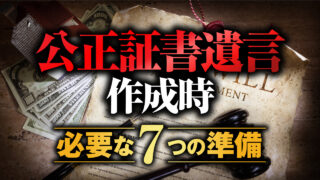「日本での活動が変わるんだけど、手続きってどうすればいいの?」
「ビザの期限が迫ってるけど、まだ日本にいたい…」
そんな時に必要なのが「在留資格変更許可申請」です。
でも正直、「手続きが複雑そう…」「必要な書類が分からない…」「もし失敗したらどうしよう…」って不安になりますよね。
大丈夫です!この記事では、1000件以上のお客様をサポートしてきた経験をもとに、在留資格変更の「分からない」を「分かる」に変えるお手伝いをします。
難しい専門用語は使わず、だれでも理解できるように優しく解説していきますね。
目次
そもそも「在留資格変更許可申請」って何?
簡単に言うと、「今のビザとは違う活動をしたい時に必要な手続き」です。
なぜこの手続きが必要なの?
日本では、外国人の方がどんな活動をできるかが、ビザ(在留資格)ごとに決められているんです。
「留学」ビザの人 → 基本的に勉強専用
「技術・人文知識・国際業務」ビザの人 → 決められた仕事のみ
もし違う活動をしたくなったら、事前にビザを変更する必要があるということです。
どんな時に在留資格変更が必要になるの?
よくあるパターンをご紹介しますね。あなたの状況と照らし合わせてみてください。
| 今のビザ | 変更先のビザ | こんな時 |
|---|---|---|
| 留学 | 技術・人文知識・国際業務 | 大学や専門学校を卒業して、日本の会社で働く |
| 就労系ビザ | 日本人の配偶者等 | 日本人と結婚した |
| 技能実習 | 特定技能 | 実習が終わって、同じ分野で働き続けたい |
| 家族滞在 | 技術・人文知識・国際業務 | 扶養を受けていた方が、学校を卒業するなどして、自ら就職する場合(資格外活動の範囲を超える場合)。 |
いつ申請すればいいの?ベストタイミングを教えます
結論から言うと、「新しい活動を始める前」に申請する必要があります。
具体的なタイミング例
就職の場合:内定をもらって雇用契約を結んだ後、実際に働き始める前
結婚の場合:婚姻届を提出して、新しい生活が始まった段階
期限に関する重要なポイント
現在のビザの有効期限内に申請しましょう。
もし審査中に期限が切れても、「特例期間」という制度があるので大丈夫です。でも、余裕を持って申請するのがベストですね。
- 審査が長引くと特例期間を超過する可能性
- 不許可になった時の対応時間がない
- 焦りから書類ミスが発生しやすい
申請の流れを分かりやすく解説
手続きの全体像を把握しておきましょう。
基本的な申請の流れ
- 情報収集・相談 – 必要な手続きと書類を確認
- 書類準備・作成 – 必要書類を集めて申請書を作成
- 申請 – 入国管理局(入管)に書類を提出
- 審査 – 結果を待つ(通常2週間〜1ヶ月)
- 結果通知 – ハガキで結果が届く
- 新しいビザ受領 – 許可された場合、新しい在留カードを受け取る
💡 プロに任せるメリット
申請取次行政書士に依頼すると、原則として入管に行く必要がありません。
書類作成から申請、結果受領まで全て代行してもらえるので、忙しい方にはとても便利ですよ。
申請場所について
申請は、あなたが住んでいる地域を管轄する入国管理局で行います。
オンライン申請も可能になっています!
メリット:24時間申請可能、待ち時間なし
デメリット:マイナンバーカードが必要、システム操作に慣れが必要
必要な書類を整理しよう
「書類が複雑で分からない…」という声をよく聞きます。でも大丈夫、整理して説明しますね。
どんな場合でも共通で必要な書類
・在留資格変更許可申請書(入管のHPからダウンロード)
・写真1枚(縦4cm×横3cm、3ヶ月以内に撮影)
・パスポート
・在留カード
ケース別の追加書類(主なもの)
留学 → 就職(技術・人文知識・国際業務)の場合
あなたについて
- 卒業証明書・成績証明書
- 専門士の証明書(専門学校卒の場合)
- 日本語能力の証明書(必要に応じて)
会社について
- 雇用契約書
- 会社の登記簿謄本
- 会社のパンフレット
- 決算書類
- 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
就職 → 結婚(日本人の配偶者等)の場合
- 日本人配偶者の戸籍謄本
- 外国人配偶者の結婚証明書(翻訳付き)
- 住民票
- 課税証明書・納税証明書
- 身元保証書
- 質問書
- 夫婦の写真数枚

申請書の書き方で失敗しないコツ
申請書は審査官が最初に見る「あなたの顔」です。ここでミスをすると印象が悪くなってしまうので、注意深く作成しましょう。
よくある失敗例と対策
基本情報の間違い → 氏名、生年月日などをパスポート通りに正確に
職務内容の説明不足 → 具体的に何をする仕事なのかを詳しく書く
他の書類との矛盾 → 申請書と雇用契約書の内容を一致させる
申請理由が不明確 → なぜこの変更が必要なのかを明確に説明
「理由書」の重要性
申請書だけでは伝わらない、あなたの事情や思いを審査官に伝えるための大切な書類です。
理由書作成のポイント
- 具体性:何をするのか具体的に
- 一貫性:他の書類と矛盾しないように
- 説得力:なぜ必要なのかを論理的に
- 継続性:今後も安定して活動できることを示す
審査にかかる時間と許可のポイント
審査期間の目安
公式には2週間〜1ヶ月とされていますが、実際はケースによって異なります。
審査が長引く要因
- 申請内容が複雑
- 書類に不備がある
- 入管の繁忙期(春の卒業・就職シーズンなど)
- 詳細な調査が必要
許可を得るために入管が見ているポイント
- 在留資格に合った活動か – 申請する活動内容がビザの内容と合っているか
- 法律の基準を満たしているか – 学歴、職歴、給与などの条件をクリアしているか
- 素行は良好か – 法律を守って生活しているか
- 生活は安定しているか – 十分な収入があるか
- 受け入れ機関は信頼できるか – 会社の経営状況は安定しているか
- 提出書類は正確か – 嘘や間違いがないか
もし不許可になってしまったら?
万が一不許可になっても、諦める必要はありません。適切な対処法があります。
まずやるべきこと
- 冷静になる – パニックにならずに状況を整理
- 理由を確認する – 入管に行って不許可の理由を聞く
- 対策を考える – 理由を解消できるかどうか検討
不許可後の選択肢
・再申請 – 理由を解消できれば再チャレンジ可能
・別のビザへの変更 – 他の在留資格の可能性を探る
・出国準備のための特定活動 – 帰国準備期間として30日程度
・帰国 – 他に選択肢がない場合
よくある質問にお答えします
Q: 申請は必ず許可されますか?
A: 残念ながら保証はありません。でも、適切な準備と書類作成を行えば、許可の可能性を大幅に高めることができます。私たちの事務所では、これまで100%の許可取得率を維持しています。
Q: 自分で申請することはできますか?
A: もちろん可能です。ただし、専門知識が必要で時間もかかります。「時間がない」「確実に成功させたい」という方は、専門家への依頼を検討してみてくださいね。
Q: 申請中に在留期限が切れそうです…
A: 大丈夫です!期限内に申請していれば、特例期間があるので適法に滞在できます。ただし、余裕を持って申請するのがベストです。
成功事例
ケース1: Aさん(28歳、中国出身)
留学ビザから就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)への変更を希望。
IT企業への就職が決まっていましたが、在留資格変更の経験がなく不安を感じていました。当事務所が全面的にサポートし、1ヶ月半で許可を取得。無事に新しい職場でキャリアをスタートさせることができました。
ケース2: Bさん(35歳、ベトナム出身)
技能実習から特定技能への在留資格変更を希望。
言語の壁に不安を感じていましたが、当事務所の多言語対応で安心して申請を進めることができました。2ヶ月で許可を取得し、同じ会社でより高度な業務に従事することが可能になりました。
専門家に依頼するメリット
「自分でやるか、専門家に頼むか…」迷いますよね。それぞれのメリットを整理してみました。
行政書士に依頼する主なメリット
- 時間の節約 – 複雑な書類作成や入管での待機から解放
- 精神的な負担軽減 – 「書類は大丈夫かな…」という不安から解放
- 許可の可能性向上 – 専門知識と経験に基づく最適な申請
- 入管への出頭不要 – 申請から受領まで代行
- トラブル対応 – 追加書類の指示や面談にも対応
費用の目安
一般的に10万円〜20万円程度が相場です。申請の難易度や内容によって変動します。
私たちがお手伝いできること
やさしい行政書士事務所では、以下の強みを活かしてサポートしています:
- 1000件以上の実績 – 豊富な経験で最適なアドバイス
- 100%の許可取得率 – 現在まで全てのお客様が許可を取得
- LINE相談対応 – 気軽にいつでもご相談
- 夜間・土日相談可 – お忙しい方にも対応
- 初回相談無料 – まずはお気軽にご相談を
- AI活用による効率化 – よりスピーディーで正確なサービス
まとめ:あなたの日本生活を全力サポートします
在留資格変更許可申請は、確かに複雑な手続きです。でも、適切な準備と知識があれば、決して不可能なことではありません。
大切なのは:
- 早めの準備 – 余裕を持って取り組む
- 正確な情報収集 – 最新で正しい情報を得る
- 丁寧な書類作成 – 審査官に伝わりやすく
- 専門家の活用 – 必要に応じてプロの力を借りる
もし「一人では不安…」「確実に成功させたい…」と思われたら、私たちのような専門家にご相談ください。
あなたの日本での新しいスタートを、全力でサポートします。一緒に頑張りましょう!
【お問い合わせはこちら】
やさしい行政書士事務所
代表行政書士 宮本 雄介
所在地: 〒257-0003 神奈川県秦野市南矢名2123-1
電話番号: 0463-57-8330 (受付時間:平日9:00~18:00)
メール: info@yusukehoumu.com
ウェブサイト: https://yusukehoumu.com/
▼LINEでのお問い合わせも可能です!▼
LINEで無料相談を予約する
初回相談は無料です。オンライン相談、夜間・土日相談(要予約)、訪問相談も承ります。お気軽にご連絡ください。
<<<TOPページへ>>>
◆お問合せフォーム
お問い合わせ内容は、公開されません。
安心してご記入ください。