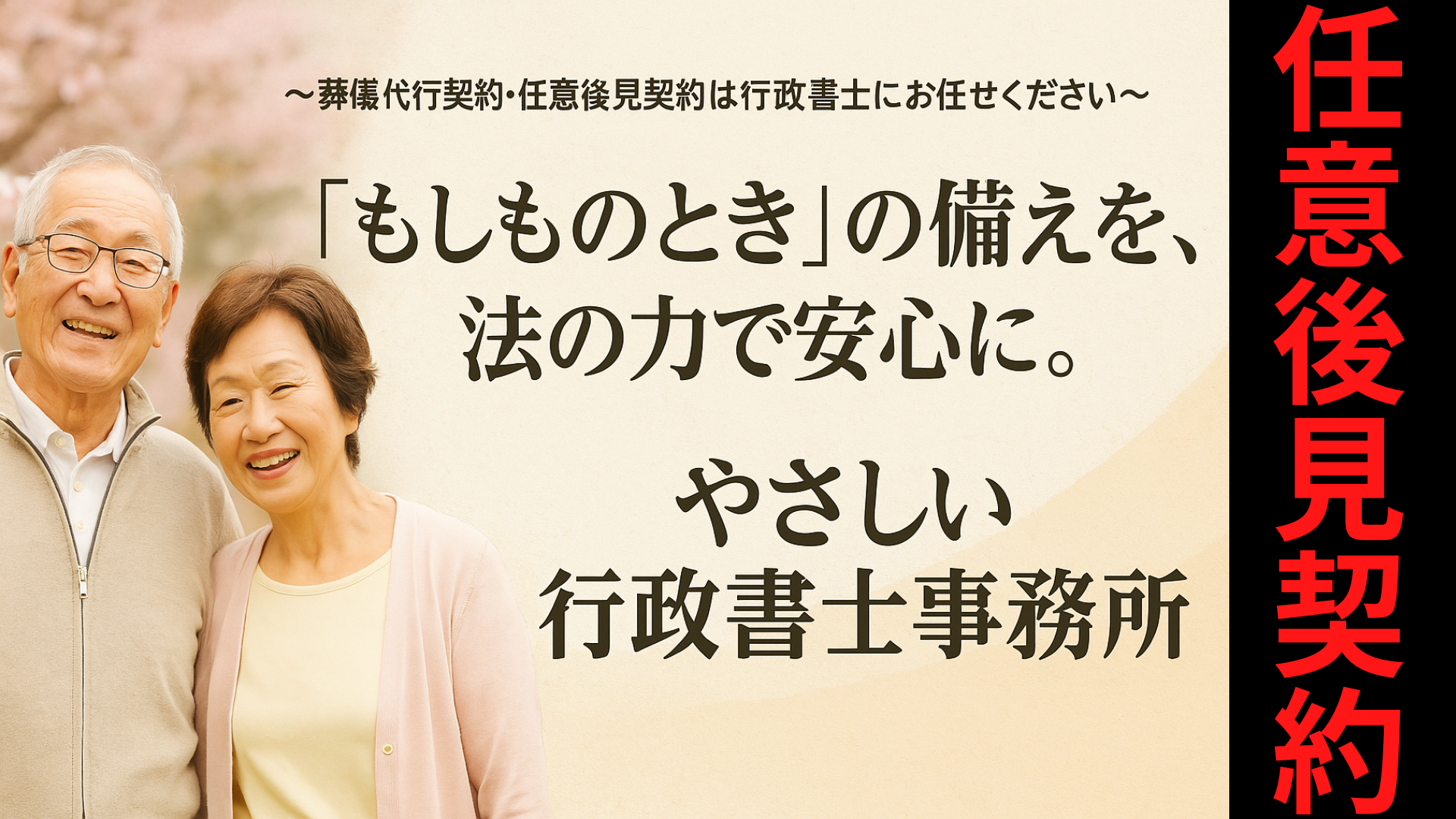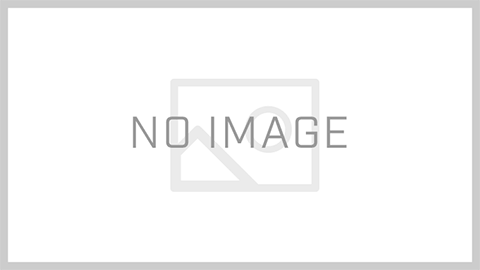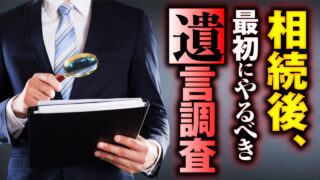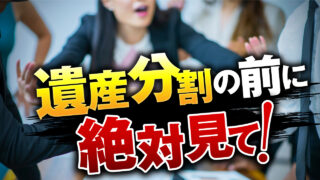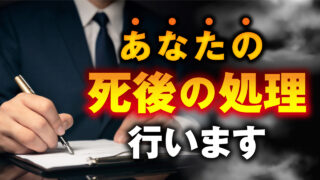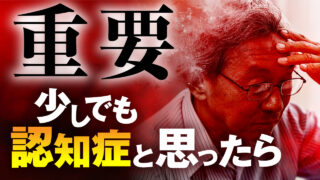目次
🌟 こんな不安はありませんか?
「将来認知症になったら、誰が私の財産を守ってくれるの?」
「望まない施設に入れられたりしないかな…」
そんな心配を解消してくれるのが「任意後見契約」です!
元気なうちに、信頼できる人に将来のことを託せる安心の制度なんです。
この記事では、1000件以上の相談実績を持つ「やさしい行政書士事務所」が、任意後見契約について分かりやすく解説していきますね。
難しい法律用語は使わず、中学生でも理解できるように説明しますので、最後まで安心して読み進めてください!
任意後見契約って、そもそも何なの?
簡単に言うと「未来の自分への保険」です
任意後見契約とは、元気なうちに「もし将来、判断力が衰えたら、この人にお任せします」という約束をしておく契約のことです。
例えば、こんなことを信頼できる人にお願いできます:
💰 お金の管理
- 銀行からお金を引き出したり、振り込んだり
- 年金を受け取ったり、税金や光熱費を払ったり
- 必要に応じて不動産を売ったり貸したり
🏠 生活のサポート
- 介護サービスの契約
- 入院や施設入所の手続き
- 住まいに関する契約
重要なのは、あなた自身で「誰に」「何を」お願いするかを決められることです!
📋 契約のルール
この契約は「公正証書」という公的な書類で作る必要があります。これによって、契約内容が明確になり、後々のトラブルを防げるんです。
いつから効力が発生するの?
契約を結んだらすぐに始まるわけではありません。
実際に効力が発生するのは:
- あなたの判断力が実際に低下した時
- 家庭裁判所に申し立てをして
- 「任意後見監督人」という見張り役の人が選ばれた時
つまり、必要になった時から始まる、とても合理的な仕組みなんですね。
なぜ今、任意後見契約が注目されているの?
時代の変化が背景にあります
最近、任意後見契約への関心がどんどん高まっています。その理由は…
👴超高齢社会の到来
65歳以上の5人に1人が認知症になると言われています。もう他人事ではないんです。
👨👩👧👦家族のカタチの変化
核家族化で頼れる親族が近くにいない、「おひとりさま」の高齢者も増えています。
💭「自分のことは自分で決めたい」という想い
法定後見制度だと、裁判所が後見人を決めるので「知らない人に財産を任せるのは不安…」という方が多いんです。
やさしい行政書士事務所にも、「子どもは遠方にいて迷惑をかけたくない」「信頼できるプロに頼みたい」といった様々なご相談が寄せられています。
任意後見と法定後見って何が違うの?
一番の違いは「誰が後見人を選ぶか」です
| 項目 | 任意後見 | 法定後見 |
|---|---|---|
| 後見人を選ぶのは | あなた自身 | 家庭裁判所 |
| 手続きを始めるのは | 元気なうち | 判断力が低下してから |
| あなたの希望の反映 | 十分に可能 | 限界がある |
| 取消権(悪い契約を取り消す権利) | なし | あり |
やさしい行政書士事務所では、「自分の意思で信頼できる人を選べる」という点が任意後見契約の最大の魅力だと考えています。
「いざという時に、知らない人が自分の財産を管理するかもしれない」という不安より、元気なうちに自分で選んでおく安心感の方がずっと大きいですからね。
任意後見契約のメリット・デメリット
🌟 メリット
👥信頼できる人を自分で選べる
家族、友人、専門家…誰でも「この人なら安心」と思う相手を選べます。やさしい行政書士事務所も任意後見受任者をお引き受けすることができます。
📝お願いする内容を細かく決められる
「不動産は売らないで」「この施設に入りたい」など、あなたの希望を具体的に契約に盛り込めます。
😊将来への安心感が得られる
「○○さんに任せてあるから大丈夫」と思えることで、日々の生活も安心して送れます。
🔄柔軟な制度設計が可能
「見守り契約」や「死後事務委任契約」と組み合わせることで、より包括的な備えができます。
⚠️ デメリット・注意点
💰監督人の費用がかかる
任意後見が始まると、必ず「任意後見監督人」という見張り役が選ばれ、月額1〜3万円程度の費用がかかります。
❌取消権がない
悪い契約をされても、後見人が取り消すことはできません。ただし、定期的な見守りでリスクを軽減できます。
⚰️死後の手続きはカバーされない
葬儀や遺品整理などは別途「死後事務委任契約」が必要です。
やさしい行政書士事務所では、これらのデメリットを補う方法も含めてご提案させていただきます。取消権がない点については、定期的な見守りや他の契約との組み合わせでカバーできるんです。
手続きの流れ
STEP1: 契約を結ぶまで
- 専門家に相談
まずは行政書士などに相談しましょう。
やさしい行政書士事務所では初回相談は無料です! - 任意後見人を決める
誰にお願いするかを決めて、その方に承諾をもらいます。 - 契約内容を決める
何をどこまでお願いするか、報酬はどうするかなどを具体的に決めます。 - 必要書類を準備
戸籍謄本、住民票、印鑑証明書などが必要です。 - 公正証書を作成
公証役場で正式な契約書を作ります。
STEP2: 契約後の流れ
- 登記
契約内容が法務局に登録されます。 - 待機期間
あなたが元気な間は、契約は「眠っている」状態です。 - 効力発生
判断力が低下したら、家庭裁判所に申し立てて監督人を選んでもらい、契約がスタートします。
やさしい行政書士事務所では、これらの手続きを最初から最後まで丁寧にサポートいたします。LINEでの進捗報告も行っているので安心ですよ。
気になる費用は?
契約時にかかる費用
| 項目 | 目安金額 | 内容 |
|---|---|---|
| 公証役場の費用 | 約1.5万円 | 公正証書作成、登記手続きなど |
| 行政書士報酬 | 79,800円 +税 | 相談、書類作成、手続きサポートなど |
| 合計目安 | 10万円程度 | 事案により変動 |
契約開始後にかかる費用
- 任意後見人への報酬:相場は月額1〜6万円程度(当事務所は月額1.1万円から)
- 任意後見監督人への報酬:月額1〜3万円程度
- その他実費:交通費、通信費など
やさしい行政書士事務所では、ご依頼前に必ず明確な見積もりをお出しします。追加費用の可能性も含めて丁寧にご説明しますので安心してください。
🌟 やさしい行政書士事務所のサポート
✨ 1000件以上の相談実績
豊富な経験に基づく、オーダーメイドの契約書作成
📱 LINE相談OK
気軽にご質問・ご相談いただけます
🏠 訪問相談対応
ご自宅や施設への訪問も可能です
🌙 夜間・土日相談
事前予約で時間外のご相談も承ります
💻 AI技術も活用
最新技術で、より迅速・的確なサポートを提供
📞 初回相談無料
0463-57-8330(平日9:00〜18:00)
まとめ:あなたらしい老後のために
任意後見契約は、「自分の未来は自分で決める」ための素晴らしい制度です。
「まだ元気だから大丈夫」と思っていても、認知症や突然の病気はいつ起こるか分かりません。
でも大丈夫です。元気な今だからこそ、しっかりと準備ができるんです。
こんな方におすすめ
- ・信頼できる人に将来を託したい
- ・自分の意思を尊重してもらいたい
- ・家族に負担をかけたくない
- ・「おひとりさま」で将来が不安
- ・具体的な希望がある
やさしい行政書士事務所では、あなた一人ひとりの想いに寄り添い、最適な任意後見契約をお手伝いします。
初回相談は無料です。「何から始めればいいか分からない」という方も、お気軽にお声かけください。
あなたらしい、安心できる未来のために、一緒に第一歩を踏み出しませんか?
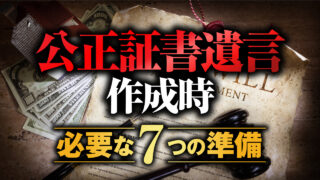
【お問い合わせはこちら】
やさしい行政書士事務所
代表行政書士 宮本 雄介
所在地: 〒257-0003 神奈川県秦野市南矢名2123-1
電話番号: 0463-57-8330 (受付時間:平日9:00~18:00)
メール: info@yusukehoumu.com
ウェブサイト: https://yusukehoumu.com/
▼LINEでのお問い合わせも可能です!▼
LINEで無料相談を予約する
初回相談は無料です。オンライン相談、夜間・土日相談(要予約)、訪問相談も承ります。お気軽にご連絡ください。
<<<TOPページへ>>>