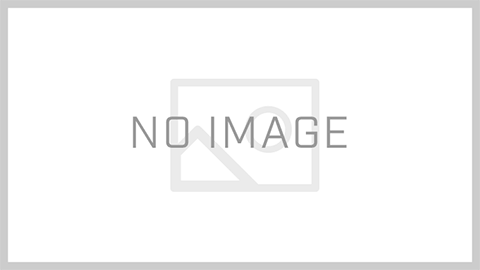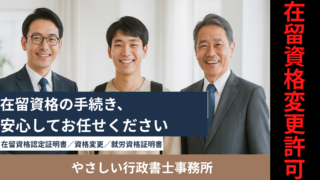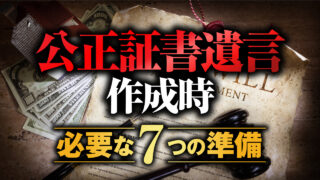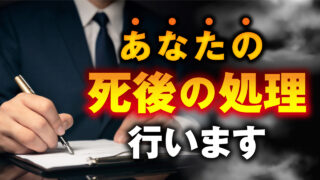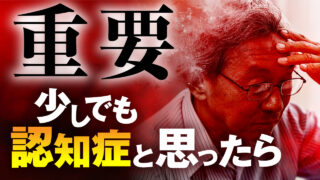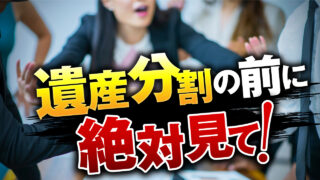・「日本で安心して暮らしたい」
・「日本人として生活したい」
と思ったことはありませんか?
帰化申請は複雑で大変そうに見えますが、正しい知識とサポートがあれば、きっと叶えることができます。
この記事では、1000件以上の相談実績を持つ専門家が、帰化申請について分かりやすく解説します!
目次
帰化申請って何?メリット・デメリットを知ろう
帰化申請とは「日本人になること」
帰化申請とは、外国籍の方が日本の国籍を取得するための手続きです。
簡単に言うと、「日本人になること」ですね。
帰化が許可されると:
日本の戸籍ができる
日本のパスポートが取得できる
選挙権・被選挙権がもらえる
ビザ更新の心配がなくなる
帰化のメリット・デメリット
✅ 帰化のメリット
ビザ更新の心配がない
– もうオーバーステイを心配する必要がありません
選挙に参加できる
– 日本の政治に参加できます
公務員になれる
– 職業選択の幅が広がります
社会的信用が上がる
– ローンが組みやすくなることも
子どもの将来が安定
– お子さんも日本人として生活できます
⚠️ 帰化のデメリット
元の国籍を失う
– 日本は二重国籍を認めていません
母国への帰国にビザが必要
– 故郷に帰るのにビザが必要になることも
手続きが複雑で時間がかかる
– 1年以上かかることが普通です
永住権と帰化、どちらがいい?
「永住権があれば十分じゃない?」と思う方もいますよね。
確かに永住権でも日本にずっと住むことはできますが、大きな違いがあります。
| 項目 | 帰化(日本国籍) | 永住権 |
|---|---|---|
| 国籍 | 日本 | 元の国のまま |
| 選挙権 | あり | なし |
| 強制退去 | 原則なし | 重大な犯罪でありうる |
| 手続きの難易度 | やや難しい | 比較的易しい |
どちらがいいかは、あなたの価値観や将来の計画によって変わります。
迷ったときは、経験豊富な専門家に相談するのが一番ですね。
帰化申請の7つの要件 – あなたは当てはまる?
帰化申請には、国の法律で決められた7つの要件があります。
「難しそう…」と思うかもしれませんが、一つずつ確認していけば大丈夫ですよ!
要件1:住所要件 – 日本に5年以上住んでいること
原則として、引き続き5年以上日本に住んでいる必要があります。
※ただし、日本人と結婚している方などは、この期間が短くなることもあります。
要件2:能力要件 – 18歳以上であること
申請時に18歳以上である必要があります。
お子さんが親と一緒に申請する場合は、この要件は不要です。
要件3:素行要件 – 真面目に生活していること
これが一番重要で、厳しくチェックされる要件です。
チェックポイント
税金をきちんと納めているか
年金・健康保険料を払っているか
交通違反を繰り返していないか
犯罪歴がないか
要件4:生計要件 – 安定した収入があること
自分や家族の収入で、安定した生活を送れることが必要です。
目安として、世帯で年収300万円程度あれば安心とされています。
正社員でなくても、安定した収入があればOKです。
要件5~7:その他の要件
重国籍防止要件:元の国籍を失うこと
憲法遵守要件:日本の法律を守ること
日本語能力:小学3〜4年生レベルの日本語力
帰化申請の流れ – step by stepで解説
帰化申請は長い道のりですが、一歩ずつ進めていけば大丈夫です。
全体で1年~1年半かかることが多いですが、しっかり準備すれば必ず到達できますよ。
STEP1 法務局で事前相談
まずは管轄の法務局に相談予約を取ります。
混雑していることが多いので、早めの予約がおすすめです。
STEP2 必要書類の収集
これが一番大変なステップです。
日本の書類だけでなく、本国の書類も必要になります。
本国の書類は取得に時間がかかるので、早めに手配しましょう。
STEP3 申請書類の作成
履歴書、動機書など、指定の様式に記入します。
動機書は特に重要で、あなたの想いを伝える大切な書類です。
STEP4 法務局に申請
必要書類が全て揃ったら、法務局に申請します。
本人が直接行く必要があります。
STEP5 面接
申請から2〜3ヶ月後に面接があります。
緊張するかもしれませんが、正直に、誠実に答えることが大切です。
STEP6 審査
面接後、8ヶ月〜1年程度の審査期間があります。
長い期間ですが、結果を待ちましょう。
STEP7 結果通知
許可されれば、官報に名前が載り、日本の戸籍が作られます。
おめでとうございます!あなたも晴れて日本人です。
必要書類は何がいる?翻訳も必要?
帰化申請で一番大変なのが、書類の準備です。
人によっては100枚を超えることもありますが、一つずつ確実に集めていきましょう。
基本的な書類
帰化許可申請書: 氏名、住所、職業などを記入。顔写真(5cm×5cm)を貼付。
親族の概要を記載した書面: 父母、兄弟姉妹、配偶者、子などの情報を記載。
履歴書: 出生から現在までの居住歴、学歴、職歴、出入国歴などを詳細に記載。
帰化の動機書: なぜ帰化したいのか、日本でどう生きていきたいかを自分の言葉で記述(15歳未満は原則不要)。
宣誓書: 日本国憲法を遵守することなどを誓約する書面(申請時に法務局で署名)。
生計の概要を記載した書面: 収入、支出、資産、負債などを記載。
事業の概要を記載した書面: 会社経営者や個人事業主の場合に必要。
自宅・勤務先・事業所付近の略図: 手書きの地図。
身分関係の書類
【本国発行】出生証明書: 申請者本人、子、兄弟姉妹などのもの。
【本国発行】婚姻証明書: 申請者本人、父母などのもの。
【本国発行】離婚証明書: 該当する場合。
【本国発行】死亡証明書: 父母、兄弟姉妹、配偶者などが死亡している場合。
【本国発行】親子関係証明書、認知届証明書、養子縁組証明書など: 該当する場合。
【本国発行】国籍証明書: 無国籍の場合や、国籍を証明する必要がある場合。
【本国発行】戸籍謄本、除籍謄本: 韓国籍の方など、戸籍制度がある国の場合。
パスポートのコピー: 現在有効なものだけでなく、失効したものも必要。出入国のスタンプがあるページも含む。
【日本発行】住民票: 世帯全員分で、続柄、国籍、在留資格、在留期間、マイナンバー省略のもの。
【日本発行】戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍: 申請者や親族が元日本人、日本で出生・婚姻・死亡等の届出をしている、日本人と婚姻・離婚しているなどの場合に必要。
【日本発行】戸籍の附票: 過去の住所歴を証明するために必要な場合。
収入・納税関係の書類
■ 生計能力を証明する書類
- 在勤及び給与証明書: 会社員の場合、勤務先に発行を依頼。
- 源泉徴収票: 直近年度分。
- (確定申告が必要な方)確定申告書(控): 個人事業主、不動産収入がある方、副業収入がある方など。第一表、第二表、青色申告決算書または収支内訳書など一式。
- (市区町村発行)所得証明書、課税(非課税)証明書: 直近年度分(または複数年分)。
- 預貯金通帳のコピーまたは残高証明書: 収入の振込や生活費の支出状況がわかるもの。
- (不動産を所有している場合)不動産登記簿謄本(登記事項証明書)、固定資産評価証明書。
- (事業を営んでいる場合)営業許可証などのコピー、会社の登記事項証明書。
- 奨学金やローンの返済予定表など。
■ 納税状況を証明する書類
- (市区町村発行)住民税(特別区民税・都民税)の納税証明書: 直近年度分(または複数年分)。未納がないことの証明。
- (税務署発行)国税の納税証明書:
- 会社員で確定申告不要な方: 原則不要な場合が多い。
- 確定申告をしている個人事業主・経営者など:
- 納税証明書(その1:納付すべき税額等の証明)
- 納税証明書(その2:所得金額の証明)
- 場合により、納税証明書(その3:未納税額のない証明)や(その4:滞納処分を受けたことのない証明)
- 対象税目:申告所得税、消費税、法人税、源泉所得税など。
- 年金・医療保険料の納付状況がわかるもの:
- ねんきん定期便、年金事務所発行の納付証明書、国民年金保険料領収証書のコピーなど。
- 健康保険証のコピー、国民健康保険料の納付証明書や領収証書のコピーなど。
■ その他の書類
その他、個別の事情に応じて必要な書類(例:離婚後の養育費支払証明、示談書のコピーなど)。
最終学歴の卒業証明書または卒業証書のコピー。
運転免許証のコピー(両面)。
運転記録証明書(または運転免許経歴証明書): 過去5年分。自動車安全運転センターで取得。
技能・資格を証明する書類: 日本語能力試験(JLPT)の合格証、その他業務に関する資格証など。
スナップ写真: 家族との写真、自宅内の写真など、生活状況を示すものとして求められる場合がある。
■ 外国語書類の日本語翻訳
- 本国の証明書など、外国語で記載された全ての書類には、原則として日本語の翻訳文を添付する必要があります。
- 翻訳文には、「翻訳者」の氏名・住所・連絡先・翻訳年月日を記載し、翻訳者が署名または押印する必要があります。
翻訳について
外国語の書類には、日本語の翻訳文を付ける必要があります。
費用と期間はどのくらい?
費用について
帰化申請は、申請手数料が無料です!
実際にかかる費用:
書類取得費用:数千円〜数万円
翻訳費用:自分でやれば無料、業者に頼むと数万円
専門家報酬:149,800円 +税
期間について
帰化申請は、準備から許可まで1年〜1年半が一般的です。
書類準備:2〜6ヶ月
審査期間:8ヶ月〜1年
期間が長くなるケース:
書類に不備がある
家族構成が複雑
過去に問題がある
法務局が混雑している
不許可になるケースと対策
せっかく時間をかけて準備したのに、不許可になってしまうのは避けたいですよね。
主な不許可理由を知って、事前に対策しましょう。
不許可の主な理由
- 税金・年金の未納 – 必ず完納してから申請を
- 交通違反の繰り返し – 安全運転を心がけましょう
- 収入が不安定 – 安定した仕事に就くことが大切
- 書類の不備・虚偽記載 – 正直に、正確に記載しましょう
- 日本語能力不足 – 面接に向けて勉強を
対策のポイント
・要件を正確に理解する
・法令遵守を徹底する
・正直かつ正確に申請する
・面接に誠実に対応する
・専門家に早期相談する
専門家に相談するメリット
「自分でもできるかな?」と思う方もいらっしゃるでしょう。
もちろん自分でもできますが、専門家に相談することで、多くのメリットがあります。
時間と労力の節約
– 複雑な手続きをお任せできます
正確な手続き
– 書類の不備を防げます
許可率向上の期待
– 経験に基づくアドバイス
精神的負担の軽減
– 「大丈夫かな?」の不安から解放
最新情報の提供
– 法改正にも対応
やさしい行政書士事務所の特徴
私たちは、これまで1000件以上の相談に対応してきました。
私たちの強み
・豊富な経験と実績 – 様々なケースに対応
・柔軟な相談体制 – LINE相談、夜間・土日対応
・分かりやすい説明 – 専門用語を使わずに丁寧に
・効率的な手続き – AIも活用したスピーディーな対応
・ワンストップサポート – 帰化後の手続きまでフォロー
「ちょっと聞いてみたい」「相談だけでも」という方も大歓迎です。
初回相談は無料ですので、お気軽にお声かけくださいね。
よくある質問
Q. 収入はどのくらい必要ですか?
A. 具体的な基準はありませんが、世帯で年収300万円程度が目安です。安定していることが重要です。
Q. 日本語はどのくらい必要ですか?
A. 小学3~4年生レベル、またはJLPTのN3程度が目安です。日常会話ができれば大丈夫です。
Q. 家族の一部だけ申請できますか?
A. 可能ですが、家族全員での申請の方が許可されやすい傾向があります。
Q. 税金の未納があったらダメですか?
A. 申請前に必ず完納する必要があります。分割納付中でも相談可能です。
まとめ – 新しい人生のスタートを一緒に
帰化申請は確かに複雑で、時間もかかります。
でも、正しい知識と適切なサポートがあれば、必ず叶えることができる目標です。
大切なのは:
・要件をしっかり理解すること
・必要な書類を正確に準備すること
・法律を守って真面目に生活すること
・分からないときは専門家に相談すること
帰化申請は、あなたの新しい人生のスタートへの第一歩です。
不安や疑問があるのは当然です。一人で悩まず、ぜひ私たちにご相談ください。
あなたの夢の実現を、全力でサポートいたします!
あなたからのご連絡を、心よりお待ちしております。一緒に、日本国籍取得という目標を実現しましょう。
【お問い合わせはこちら】
やさしい行政書士事務所
代表行政書士 宮本 雄介
所在地: 〒257-0003 神奈川県秦野市南矢名2123-1
電話番号: 0463-57-8330 (受付時間:平日9:00~18:00)
メール: info@yusukehoumu.com
ウェブサイト: https://yusukehoumu.com/
▼LINEでのお問い合わせも可能です!▼
LINEで無料相談を予約する
初回相談は無料です。オンライン相談、夜間・土日相談(要予約)、訪問相談も承ります。お気軽にご連絡ください。
<<<TOPページへ>>>
◆お問合せフォーム
お問い合わせ内容は、公開されません。
安心してご記入ください。