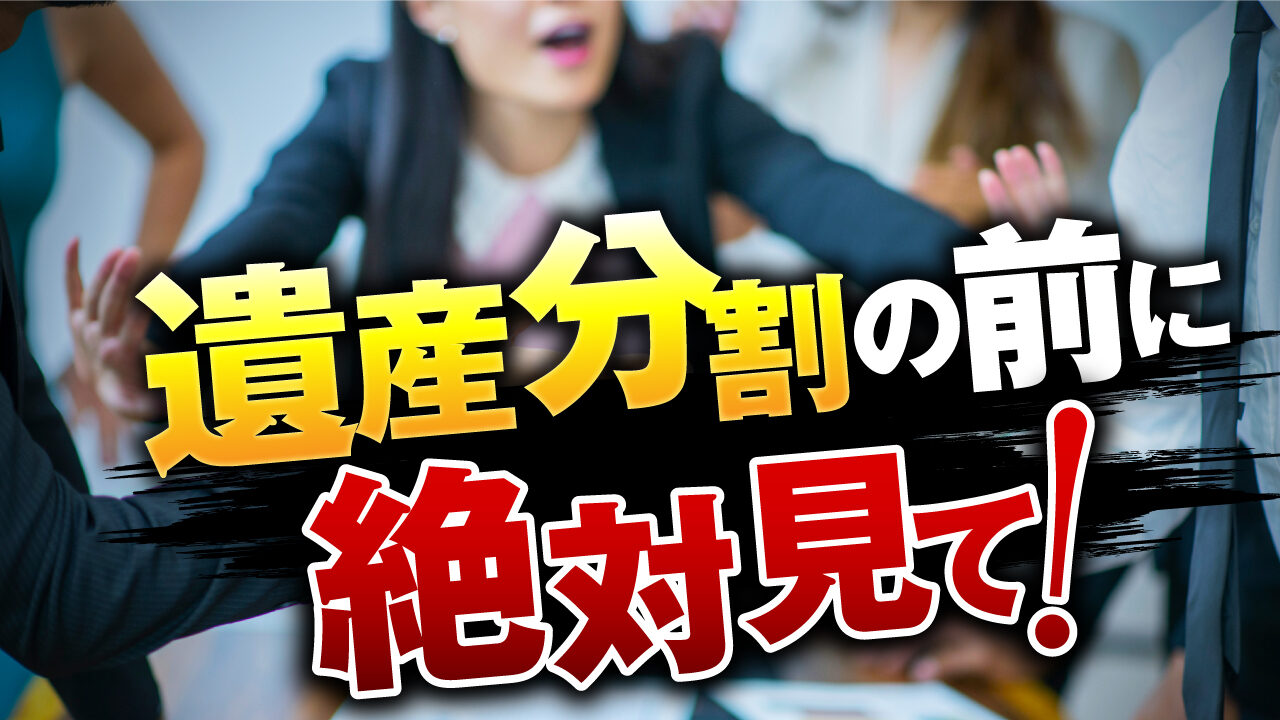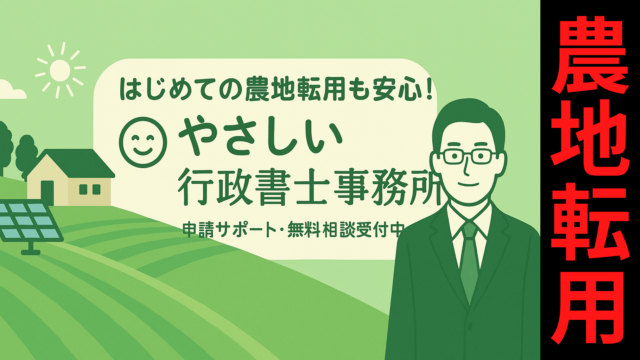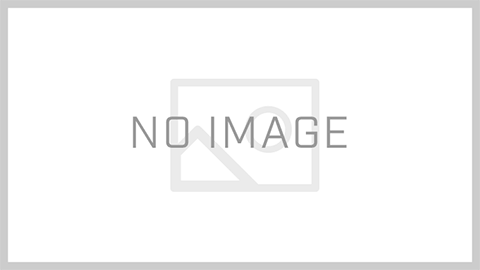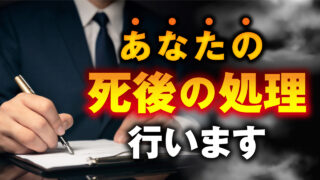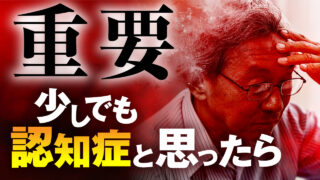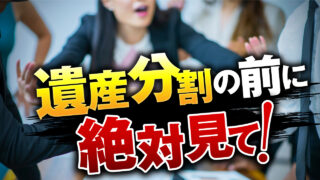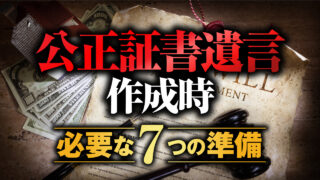・「身内が亡くなって、遺産分割って聞いたけど何をすればいいの?」
・「家族で話し合ってるけど、なかなかまとまらなくて困ってる…」
こんなお悩みを抱えている方、多いんじゃないでしょうか?
遺産分割って、なんだか複雑で難しそうですよね。でも大丈夫です!
正しい手順を踏めば、きっと円満に解決できます。
この記事では、1000件以上の相続相談を解決してきた「やさしい行政書士事務所」が、遺産分割の基本的な流れから、よくある悩みの解決方法まで、
分かりやすく、やさしくお伝えします。
目次
❓ そもそも遺産分割って何?なぜ必要なの?
遺産分割とは?
遺産分割とは、亡くなった方の財産を、相続人みんなで話し合って分けることです。
人が亡くなると、その方の財産は一旦、相続人全員の「共有」状態になります。
でも、これって実はとても不便なんです。
- ・実家を売りたくても、相続人全員の同意が必要
- ・預金を引き出すのも一苦労
- ・誰かひとりでも反対すると、何もできなくなる
遺産分割をしないとどうなる?
「面倒だから後回しに…」って思う気持ち、よく分かります。
でも、放置しているとこんなリスクがあるんです:
- ・不動産が塩漬け状態に → 売却も賃貸もできない
- ・預金が引き出せない → 生活費にも困ることが
- ・相続人がさらに増える → 時間が経つほど複雑化
- ・相続登記の義務化 → 2024年から怠ると過料の可能性
💡 やさしい行政書士事務所からのアドバイス
「まだ気持ちの整理がついていない」というお気持ち、とてもよく分かります。
でも、手続きを先延ばしにするリスクを考えると、少しずつでも進めていくことをおすすめします。
私たちは、お客様のペースに合わせて、丁寧にサポートさせていただきます。
👥 誰が相続人になるの?
遺産分割は、相続人全員で行う必要があります。
では、具体的に誰が相続人になるのでしょうか?
相続人になる人の順番
- 配偶者(夫・妻) → 必ず相続人になります
- 第1順位:子ども(子どもが亡くなっていれば孫)
- 第2順位:両親(子どもがいない場合)
- 第3順位:兄弟姉妹(子どもも両親もいない場合)
上の順位の人がいれば、下の順位の人は相続人になりません。
例えば、子どもがいれば両親は相続人になりません。
相続できる割合(法定相続分)
| 相続人の組み合わせ | 配偶者 | その他 |
|---|---|---|
| 配偶者と子ども | 1/2 | 子ども全体で1/2 |
| 配偶者と両親 | 2/3 | 両親全体で1/3 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 3/4 | 兄弟姉妹全体で1/4 |
でも、これはあくまで目安です。
みんなが合意すれば、違う割合で分けても大丈夫ですよ。
📝 遺産分割の進め方|手順を分かりやすく解説
遺産分割は、こんな流れで進めていきます:
ステップ1:相続人を調べる
まずは、誰が相続人になるかを正確に調べます。
これには戸籍謄本という書類が必要になります。
- ・亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍
- ・相続人全員の現在の戸籍
「戸籍謄本って何?どうやって取るの?」って思いますよね。
役所で取得できるのですが、実は結構読み解くのに面倒な作業があるんです…
ステップ2:財産を調べる
次に、亡くなった方がどんな財産を持っていたかを調べます。
- プラスの財産:現金、預金、不動産、株式など
- マイナスの財産:借金、ローンなど
意外と見落としがちなのが住宅ローンなどの借金です。
借金が多い場合は、相続放棄という選択肢もあります。
ステップ3:みんなで話し合い(遺産分割協議)
相続人と財産が分かったら、いよいよ話し合いです。
「誰が」「何を」「どのくらい」もらうかを決めていきます。
💡 話し合いを円滑に進めるコツ
- ・感情的にならず、冷静に話し合う
- ・お互いの意見を尊重する
- ・情報はオープンに共有する
- ・相続税の申告期限(10ヶ月)を意識する
もし話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の調停という方法もあります。
でも、できれば家族で円満に解決したいですよね。
🏢 やさしい行政書士事務所のサポート
戸籍謄本の収集から財産調査、話し合いの土台作りまで、
面倒な作業はすべて私たちがお手伝いします。
お忙しい方や、手続きが不安な方も安心してお任せください。
📋 遺産分割協議書の作り方|これで手続きもスムーズ!
話し合いがまとまったら、その内容を遺産分割協議書という書類にします。
これがないと、後の手続きが一切できないんです。
なぜ遺産分割協議書が必要?
- 口約束だけでは「言った、言わない」でトラブルになる
- 不動産の名義変更に必要
- 預金の解約・名義変更に必要
- 相続税の申告に必要
協議書に書くべき内容
- 亡くなった方の情報(氏名、住所、本籍、死亡日)
- 相続人全員で合意したという文言
- 誰がどの財産をもらうか(具体的に記載)
- 後で見つかった財産の扱い
- 作成日と相続人全員の署名・実印
特に大切なのは、財産を正確に書くことです。
不動産なら登記簿通りに、預金なら銀行名・支店名・口座番号まで、
一字一句間違えないように記載する必要があります。
- ・財産の記載が曖昧で、手続きで受理されない
- ・相続人の署名漏れで無効になる
- ・印鑑証明書の添付を忘れる
協議書ができたら次にすること
遺産分割協議書ができたら、いよいよ各種手続きです:
- 不動産の名義変更 → 司法書士に依頼
- 預金の解約・名義変更 → 各銀行で手続き
- 株式の名義変更 → 証券会社で手続き
- 相続税の申告 → 税理士に依頼(必要な場合)
✨ やさしい行政書士事務所の強み
私たちは、法的に有効で後々問題にならない協議書作成のプロです。
登記簿謄本や残高証明書をしっかり確認して、正確な書類を作成します。
相続登記や相続税申告が必要な場合は、信頼できる司法書士や税理士もご紹介できます。
😟 よくある悩みと解決法
相続人同士で意見が対立している場合
残念ながら、よくあることです。こんな場合によく揉めます:
- 実家を誰が相続するか
- 兄弟は仲がいいけど、妻同士が仲が悪い
- 不動産の評価額をいくらにするか
- 生前にもらったお金があるかないか
- 介護の貢献度をどう評価するか
大切なのは、感情的にならず、客観的な事実に基づいて話し合うことです。
注意!行政書士ができないこと
すでに争いになっている場合、行政書士は代理人として交渉することはできません。
これは弁護士の専門分野になります。
でも、争いになる前なら、私たちがお手伝いできることがあります:
- 客観的な資料(相続関係図、財産目録)の作成
- 法律上のルールについての情報提供
- 話し合いの土台となる資料の整理
分けにくい財産がある場合
現金や預金と違って、不動産や株式は簡単に分けられませんよね。
こんな方法があります:
| 方法 | 内容 | 向いているケース |
|---|---|---|
| 現物分割 | 財産そのものを分ける | 土地が広くて分筆できる場合など |
| 代償分割 | 一人が財産をもらい、他の人に現金を支払う | 実家を守りたい場合など |
| 換価分割 | 財産を売却して現金を分ける | 誰も住まない実家など |
どの方法が良いかは、財産の種類や皆さんの状況によって変わります。
一緒に最適な方法を考えていきましょう。
🤔 専門家選びのポイント|誰に相談すべき?
「結局、誰に頼めばいいの?」って迷いますよね。
専門家ごとに得意分野が違うんです:
- 行政書士 → 書類作成、争いのない相続手続き
- 弁護士 → 相続人間の争い、調停・審判
- 司法書士 → 不動産の名義変更
- 税理士 → 相続税の申告
行政書士への依頼が向いているケース
こんな状況なら、行政書士にお任せください:
🌟 やさしい行政書士事務所の特徴
私たち「やさしい行政書士事務所」は、2012年から1000件以上のご相談にお応えしてきました。
こんな方におすすめです
- 外国籍の相続人がいる方 → 国際相続の経験あり
- 高齢の方 → ご自宅への訪問相談も可能
- 忙しい経営者の方 → 夜間・土日相談対応
- 気軽に相談したい方 → LINEでのご相談もOK
私たちのサポート体制
- 📱 LINE相談対応 → 気軽にご質問いただけます
- 🏠 訪問相談 → ご自宅や施設にお伺いします
- 🌙 夜間・土日対応 → お忙しい方もご都合に合わせて
- 🌍 国際相続対応 → 外国籍の方も安心
- 💼 事業承継サポート → 経営者の方の特殊事情にも対応
📞 まずは無料相談から始めませんか?
やさしい行政書士事務所
代表行政書士 宮本 雄介
📞 0463-57-8330(平日9:00〜18:00)
📧 info@yusukehoumu.com
🌐 https://yusukehoumu.com/
初回相談無料です!
LINEでのご相談も承っています
✨ まとめ|一人で悩まず、まずは相談を
遺産分割って、確かに複雑で面倒な手続きです。
でも、正しい手順を踏めば、必ず解決できます。
この記事のポイント
「何から始めたらいいか分からない」
「家族だけで話し合うのは不安」
「正確な書類を作ってもらいたい」
そんな時は、ぜひ私たちにご相談ください。
1000件以上の経験に基づいて、
あなたの状況に最適な解決方法を一緒に考えます。
初回相談は無料です。
「ちょっと話を聞いてみたい」という段階でも大丈夫。
一人で抱え込まず、まずは気軽にお声がけください。
あなたの「やさしい相続」を実現するお手伝いをさせていただきます。
💌 最後に
遺産分割は、単なる手続きではありません。
大切な方を亡くした悲しみの中で、ご家族の絆を深める機会でもあります。
私たちは、そんな大切な時間を、より良いものにするお手伝いをしたいと思っています。

【お問い合わせはこちら】
やさしい行政書士事務所
代表行政書士 宮本 雄介
所在地: 〒257-0003 神奈川県秦野市南矢名2123-1
電話番号: 0463-57-8330 (受付時間:平日9:00~18:00)
メール: info@yusukehoumu.com
ウェブサイト: https://yusukehoumu.com/
▼LINEでのお問い合わせも可能です!▼
LINEで無料相談を予約する
初回相談は無料です。オンライン相談、夜間・土日相談(要予約)、訪問相談も承ります。お気軽にご連絡ください。
<<<TOPページへ>>>
◆お問合せフォーム
お問い合わせ内容は、公開されません。
安心してご記入ください。