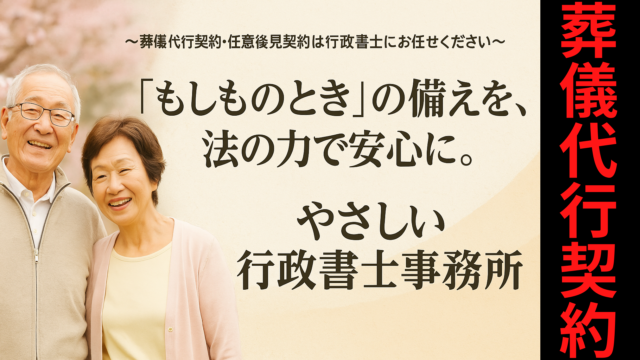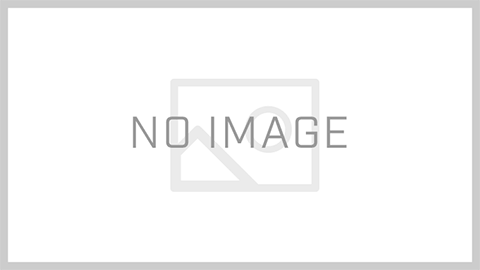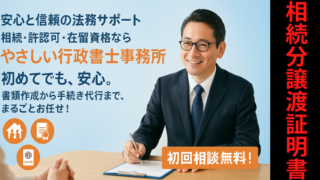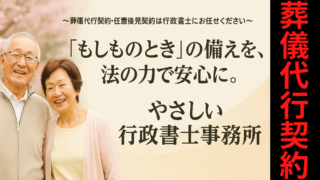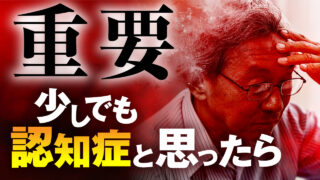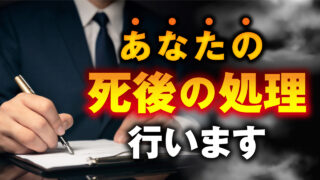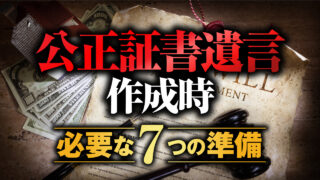目次
相続における財産目録作成とは?
財産目録作成とは、相続が発生した際に、故人(被相続人)が遺した全ての財産(不動産、預貯金、有価証券、車両、貴金属など)と債務(ローン、借入金など)を正確に把握し、一覧表にまとめる作業です。
相続手続きの第一歩として、まず「何を相続するのか」を明確にすることは非常に重要です。正確な財産目録があれば、相続人間のトラブルを未然に防ぎ、公平な遺産分割協議を進めることができます。また、相続税の申告が必要な場合には、財産目録は課税対象となる遺産総額を把握するための必須資料となります。
当事務所では、故人の遺された財産を漏れなく調査し、相続人の方々が安心して相続手続きを進められるよう、正確で分かりやすい財産目録の作成をサポートしています。
お客様に用意していただく書類と情報
相続に関する財産目録を正確に作成するため、以下の書類や情報をご準備いただく必要があります:
- 不動産関係書類
- 登記簿謄本:被相続人名義の全ての不動産情報
- 固定資産税評価証明書:相続税評価額の算出に必要です
- 不動産の賃貸借契約書(賃貸に出している場合)
- 預貯金関係
- 被相続人名義の通帳のコピー(表紙と直近数ページ分)
- 被相続人名義の全ての金融機関の残高証明書(相続発生時点のもの)
- インターネットバンキングの場合は残高画面のプリントアウト
- 有価証券関係
- 証券会社の取引残高報告書
- 株券や投資信託の明細書類
- 株主配当通知書
- 生命保険・損害保険
- 被相続人が契約者または被保険者となっている保険証券のコピー
- 死亡保険金の受取通知書(すでに受け取っている場合)
- その他の財産
- 自動車検査証(車検証)のコピー
- 貴金属・美術品等の鑑定書や購入時の領収書
- 会員権(ゴルフ会員権など)の証書
- 債務関係
- 住宅ローンなどの借入金残高証明書
- クレジットカードの利用明細・借入残高
- 未払い税金の通知書
- 葬儀費用の領収書
※全ての書類をすぐに揃える必要はありません。まずは手元にある資料をご持参いただき、当事務所と相談しながら必要な書類を集めていきましょう。亡くなられて間もない場合は、まずはご連絡ください。
依頼から完了までの標準的な期間
相続に関する財産目録の作成は、一般的に以下のような流れで進みます:
- 初回相談・ヒアリング(1日)
- 相続の状況や故人の財産についての基本情報を確認
- 相続人の確認と今後の進め方の説明
- 資料収集期間(2週間~1ヶ月)
- 相続人様による必要書類の収集
- 当事務所による金融機関等への照会・調査のサポート
- 財産目録の作成(2~3週間)
- 収集した資料をもとに相続財産の評価・積算
- 相続税の基礎控除額との比較検討
- 負債や葬儀費用等の債務控除項目の整理
- 内容確認・修正(1週間程度)
- 作成した財産目録の内容を相続人様と確認
- 必要に応じて修正・追加情報の収集
- 最終納品・今後のアドバイス(1日)
- 完成した財産目録の納品と説明
- 相続税申告の要否の判断と今後の手続きのアドバイス
標準的な所要期間は、資料がスムーズに集まった場合で約1~2ヶ月程度です。ただし、以下の要因により期間が前後する場合があります:
- 被相続人の財産が多岐にわたる場合
- 不動産や事業用資産が多い場合
- 相続開始から時間が経過している場合
当事務所では、相続の大変な時期だからこそ、進捗状況を定期的にご報告し、相続人様の負担を減らすよう努めています。
費用
基本料金:49,800円(+税)
※以下の場合は別途料金が発生する場合があります:
- 相続財産が複数の都道府県にまたがる場合
- 相続財産の種類が多岐にわたる場合(10種類以上)
- 海外に財産がある場合
- 事業用資産の評価が必要な場合
- 相続人が多数の場合
詳細な料金については、初回相談時に詳しくご説明いたします。お見積りは無料で行っていますので、ご安心ください。
よくある質問とその回答
Q1: 相続の財産目録を自分で作成することはできませんか?
A1: ご自身で作成することも可能です。しかし、相続財産の評価方法や相続税の計算に関する専門知識が必要となるため、見落としや評価ミスによって相続人間のトラブルになるケースも少なくありません。特に不動産や事業用資産の評価は専門的な知識を要します。当事務所にご依頼いただくことで、専門家の目線から漏れのない正確な財産目録を作成し、円滑な相続手続きをサポートします。
Q2: 被相続人(故人)の財産がどこにあるのか分からない場合でも依頼できますか?
A2: はい、ぜひご相談ください。当事務所では、「故人がどのような財産を持っていたか分からない」というケースも多く対応しています。金融機関への照会方法のアドバイスや、必要に応じて「相続財産調査」のサービスを通じて、被相続人の財産を調査することも可能です(別途料金がかかります)。思いがけない財産が見つかるケースも少なくありません。
Q3: 相続税の申告は必要ないと思うのですが、それでも財産目録は必要ですか?
A3: 相続税の申告が不要な場合でも、財産目録は相続人間での遺産分割協議を円滑に進めるために非常に重要です。また、将来的に「知らなかった財産」が見つかった場合のトラブル防止や、預貯金の解約、不動産の名義変更などの各種相続手続きの際の証明資料としても役立ちます。正確な財産目録は、相続手続き全体をスムーズに進めるための基礎となります。
Q4: 遺言書があっても財産目録は必要ですか?
A4: はい、遺言書があっても財産目録の作成は重要です。遺言書には具体的な財産の評価額が記載されていないことが多く、相続税の申告が必要かどうかの判断や、遺留分侵害額の計算には正確な財産評価が必要となります。また、遺言書作成後に取得・処分された財産もあるため、相続開始時点での正確な財産状況を把握することが大切です。
Q5: 相続発生から数年経っていますが、今から財産目録を作成することはできますか?
A5: はい、可能です。ただし、時間が経過するほど資料の収集が難しくなる場合があります。特に預貯金の残高証明書などは、金融機関によっては相続発生から一定期間経過すると発行してもらえないこともあります。できるだけ早めにご相談いただくことをおすすめしますが、すでに時間が経過している場合でも、当事務所ではできる限りのサポートをいたします。
事例紹介
事例1:複数の不動産と金融資産の相続を整理したAさん家族の場合
Aさん(60代男性)は、父親が亡くなり相続手続きを進める必要がありましたが、父親が複数の不動産、複数の金融機関の口座、株式、保険など多様な資産を持っていたため、何から手をつければよいか分からない状態でした。また、兄弟3人での遺産分割に不安を感じていました。
当事務所では、まず財産目録の作成からスタートし、約1ヶ月半かけて全ての財産を洗い出しました。その結果、Aさんも知らなかった株式や保険が見つかり、相続税の申告も必要であることが判明。税理士とも連携しながら、スムーズな相続手続きをサポートしました。正確な財産目録があったことで、相続人間の話し合いもスムーズに進み、公平な遺産分割が実現できました。
事例2:遠方に住む親の相続で慌てていたBさんの場合
Bさん(50代女性)は、遠方に住む母親の急な死去により相続手続きを行う必要が生じましたが、仕事が忙しく現地に何度も足を運ぶことができない状況でした。また、母親の財産状況をほとんど把握していませんでした。
当事務所では、現地での戸籍取得代行や金融機関への照会など、必要な書類の取得から財産目録の作成まで一括してサポート。オンライン面談を活用しながら、Bさんの負担を最小限に抑えつつ、約2ヶ月で財産目録を完成させ、その後の相続手続きもスムーズに進めることができました。調査の結果、予想よりも多くの預金が見つかり、Bさんは「専門家に依頼して本当に良かった」と喜ばれました。
お問い合わせ
無料相談のご予約・お問い合わせは、以下の方法で承っております:
まずは気軽にご連絡ください。お客様の日本での新生活の第一歩を、私たちがしっかりサポートいたします。
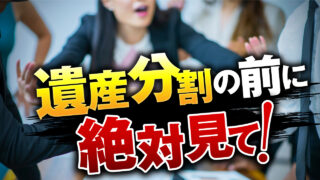
【お問い合わせはこちら】
やさしい行政書士事務所
代表行政書士 宮本 雄介
所在地: 〒257-0003 神奈川県秦野市南矢名2123-1
電話番号: 0463-57-8330 (受付時間:平日9:00~18:00)
メール: info@yusukehoumu.com
ウェブサイト: https://yusukehoumu.com/
▼LINEでのお問い合わせも可能です!▼
LINEで無料相談を予約する
初回相談は無料です。オンライン相談、夜間・土日相談(要予約)、訪問相談も承ります。お気軽にご連絡ください。
<<<TOPページへ>>>
◆お問合せフォーム
お問い合わせ内容は、公開されません。
安心してご記入ください。