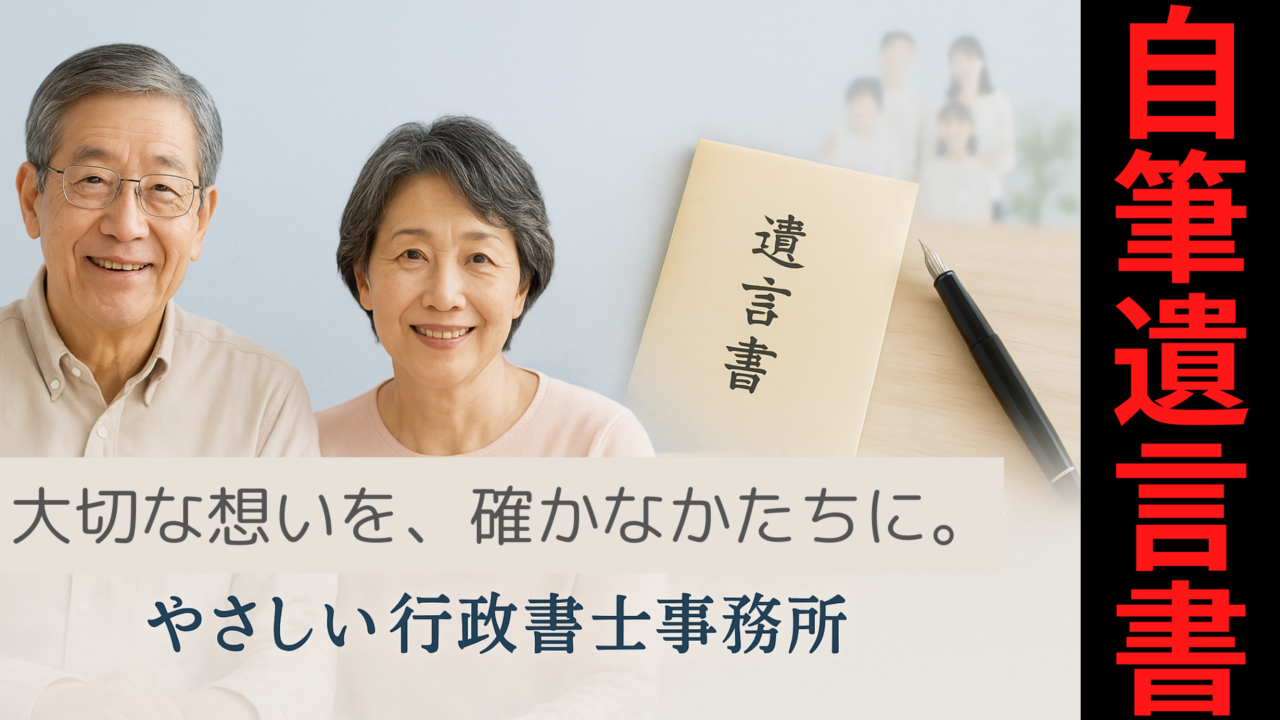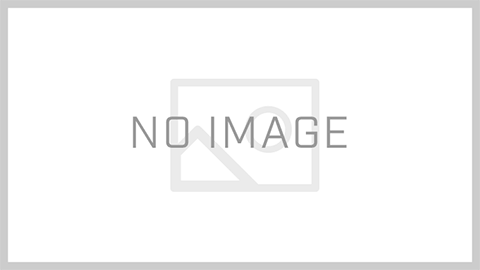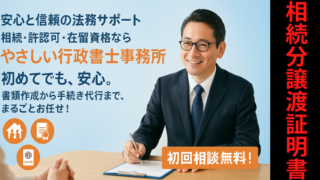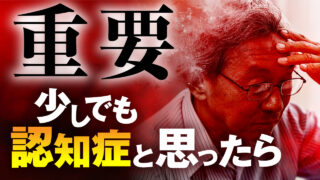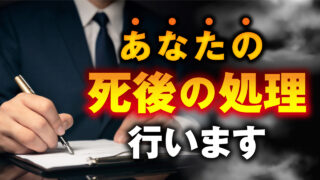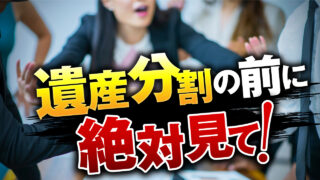目次
自筆遺言書作成サポート業務について
人生の集大成として、大切な財産を次の世代へ円滑に引き継ぐために欠かせないのが遺言書です。特に自筆遺言書は、ご自身の手で書くことで法的効力を持つ重要な書類となります。しかし、正確な法律知識がないまま作成すると、無効になってしまうリスクもあります。
当事務所では、お客様が法的に有効な自筆遺言書を作成できるよう、専門家の立場からサポートいたします。適切な文言の選定や法的要件の確認だけでなく、相続トラブルを未然に防ぐための具体的なアドバイスも提供。さらに、遺言書の保管方法や相続発生時の手続きについても丁寧にご説明します。専門家のサポートを受けることで、安心して大切な想いを形にすることができます。
ご準備いただく書類・情報
自筆遺言書作成のサポートを円滑に進めるため、以下の書類・情報をご用意ください。
- ご本人の戸籍謄本(発行から3ヶ月以内のもの)
- 遺言者様の法的身分を確認するために必要です
- 本籍地の市区町村役場で取得できます
- 相続人となる方々の戸籍謄本(可能であれば)
- 法定相続人を正確に把握するために役立ちます
- 入手が難しい場合は、氏名と続柄のメモでも構いません
- 相続財産の資料
- 不動産の登記簿謄本や固定資産税評価証明書
- 預貯金通帳のコピー
- 有価証券の残高証明書など
- 正確な財産目録作成のために必要です
- 遺言内容のメモ
- どなたにどの財産を相続させたいかをメモしておくと打ち合わせがスムーズです
- 特別な希望(お墓のこと、葬儀のことなど)があればそれも含めてください
※書類がすべて揃っていない段階でもご相談いただけます。必要に応じて当事務所でも書類取得のサポートが可能です(別途費用がかかる場合があります)。
依頼から完了までの期間
自筆遺言書作成のサポートは、通常以下のような流れで進みます。
標準的な期間:初回相談から約2〜4週間
- 初回相談(1時間程度)
- ご要望や財産状況のヒアリング
- 進め方の説明
- 資料収集・分析(1〜2週間)
- 必要書類の確認と分析
- 法的な問題点の洗い出し
- 遺言書案の作成(3〜5日)
- お客様のご意向を反映した遺言書案の作成
- 内容確認・修正(1週間程度)
- 遺言書案のご確認と必要に応じた修正
- 法的効力の最終確認
- 自筆遺言書の作成(1日)
- 当事務所にて、実際に自筆遺言書を書いていただきます
※複雑な財産状況や特殊なご要望がある場合は、期間が延びることがあります。また、お急ぎの場合は、可能な限り対応いたしますので、ご相談ください。
費用
自筆遺言書作成サポート 基本料金:29,800円(+税)
※基本料金に含まれるサービス:
- 初回相談(1時間)
- 遺言書案の作成
- 法的要件の確認
- 自筆遺言書作成のサポート
よくあるご質問
Q1. 自筆遺言書は本当に自分で書かなければならないのですか?
A. はい、自筆遺言書は民法の規定により、日付と氏名を含め全文を遺言者ご本人が自筆で書く必要があります。パソコンでの作成や代筆は認められていません。ただし、内容の検討や文言の選定などは専門家のサポートを受けることができます。当事務所では、法的に有効な文面をご提案し、実際に書いていただく際のサポートをいたします。
Q2. 体調が優れず、長文を書くのが難しいのですが対応可能ですか?
A. もちろん対応可能です。体調に配慮し、必要最小限の内容でも法的効力を持つ遺言書の作成をサポートいたします。また、自筆が困難な場合は、公正証書遺言という方法もございますので、ご状況に応じて最適な方法をご提案いたします。
Q3. 一度作成した遺言書を後から変更することはできますか?
A. はい、可能です。遺言は、お亡くなりになるまでいつでも変更・撤回することができます。内容の一部変更には「変更の遺言」を、全面的な変更には新たな遺言書の作成をおすすめします。いずれの場合も、当事務所でサポートいたしますので、ご遠慮なくご相談ください。
Q4. 遺言書の保管はどうすればよいですか?
A. 自筆遺言書は、ご自宅や銀行の貸金庫で保管する方法などがあります。また、2020年7月から始まった法務局の「自筆証書遺言書保管制度」の利用もおすすめです。この制度を利用すると、遺言書の紛失や改ざんのリスクがなく、相続発生時に法務局から相続人へ通知されるメリットがあります。当事務所では、この保管制度の利用手続きもサポートしております。
Q5. 相続人以外の人に財産を残すことはできますか?
A. はい、可能です。遺言書では、法定相続人以外の方(お世話になった方、慈善団体など)に財産を遺贈することができます。ただし、相続人には「遺留分」と呼ばれる最低限保障される取り分がありますので、その点を考慮した内容にする必要があります。当事務所では、法律上の制約を踏まえた上で、お客様のご希望に沿った遺言書作成をサポートいたします。
事例紹介
※以下は実際の事例を基にしておりますが、プライバシー保護のため一部修正しています。
【事例1】再婚後の財産分配を明確にされたAさんのケース
Aさん(70代男性)は再婚されており、前妻との間に子どもが2人、現在の奥様との間に子どもが1人いらっしゃいました。前の結婚中に取得した不動産と貯金は前妻との子どもに、再婚後に増えた財産は現在の奥様と子どもに、というご希望でした。
当事務所では、財産の取得時期を整理し、法的に有効な表現で遺言書を作成。相続人全員の遺留分も考慮した内容としました。Aさんは「これで安心して余生を過ごせる」と喜んでくださいました。
【事例2】家業の円滑な承継を実現されたBさんのケース
個人事業主のBさん(60代女性)は、3人のお子さんのうち1人だけが家業を継いでいました。事業用の不動産や設備は家業を継ぐ子に、その他の財産は残りの子どもたちに公平に分けたいというご希望でした。
遺留分も考慮しながら、事業承継がスムーズに進むよう財産の分配方法を工夫。さらに、遺言執行者(遺言内容を実現する役割の人)も指定することで、Bさんの意思が確実に実現される内容に仕上げました。
お問い合わせ
自筆遺言書作成について、少しでもご興味をお持ちいただけましたら、まずは無料相談をご利用ください。お電話またはウェブサイトのお問い合わせフォームからご予約いただけます。
無料相談では、以下の内容をお伺いします:
- ご家族構成
- 財産の概要
- 遺言でのご希望
ご相談の結果、即日にご依頼いただくことも、いったんお持ち帰りいただくことも可能です。お客様のペースに合わせて進めさせていただきますので、お気軽にご連絡ください。
当事務所は、お客様の「安心」と「想いの実現」をサポートいたします。人生の大切な決断を、専門家と一緒に進めてみませんか?
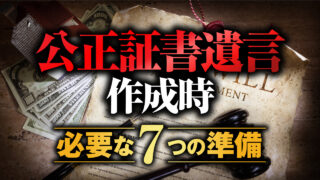
【お問い合わせはこちら】
やさしい行政書士事務所
代表行政書士 宮本 雄介
所在地: 〒257-0003 神奈川県秦野市南矢名2123-1
電話番号: 0463-57-8330 (受付時間:平日9:00~18:00)
メール: info@yusukehoumu.com
ウェブサイト: https://yusukehoumu.com/
▼LINEでのお問い合わせも可能です!▼
LINEで無料相談を予約する
初回相談は無料です。オンライン相談、夜間・土日相談(要予約)、訪問相談も承ります。お気軽にご連絡ください。
<<<TOPページへ>>>