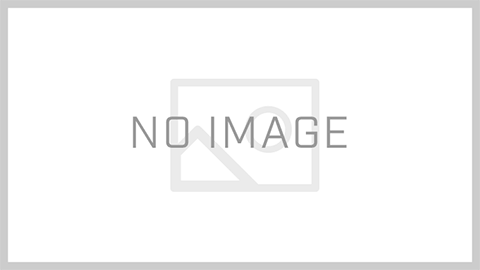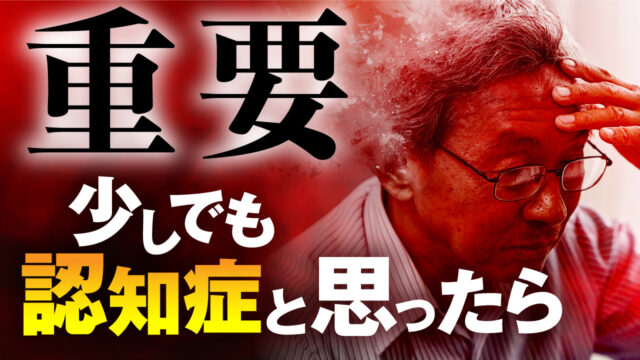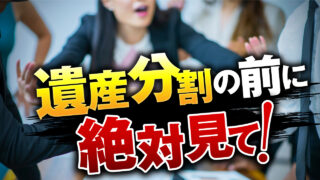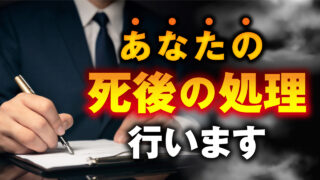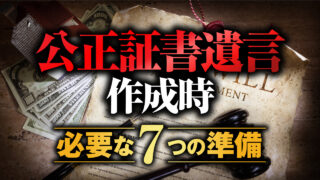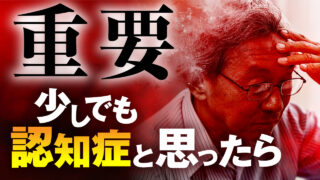こんにちは!
建設業許可って聞くと「難しそう…」「何から始めればいいの?」って思いませんか?
でも大丈夫です😊
この記事を読めば、建設業許可のことがスッキリ分かります!
こんな方にピッタリです:
・元請けから「建設業許可を取って」と言われた
・会社を作ったので建設業許可も欲しい
・500万円以上の工事を請け負う予定がある
・建設業許可の期限がもうすぐ切れそう
実は、建設業許可には7つの条件があります。
一つずつ見ていけば、そんなに難しくないんですよ!
重要な変更点(2024年法改正)
2024年6月に建設業法が大幅改正され、2024年12月13日から順次施行されています!
労働者の処遇改善、ICT活用による生産性向上、適正な契約ルールなど、建設業界の構造改革を目的とした包括的な改正です。
目次
条件1:経営のプロがいること(経営業務の管理責任者)
最も重要で複雑な条件です。
会社の常勤役員の中に、経営の責任者となれる人が必要です。
2020年法改正で選択肢が増えました!
【パターンA】一人で要件を満たす場合
次のうちどれか一つを満たす常勤役員がいればOK:
- 建設業での役員経験5年以上(一番わかりやすい!)
- 建設業での役員に準ずる地位で5年以上(執行役員など)
- 建設業での経営補佐経験6年以上(部長職など)
【パターンB】チームで要件を満たす場合(2020年新設)
中核となる役員 + 専門知識を持つ補佐者のチーム体制でも可能に!
中核となる役員の要件(以下の両方を満たす):
- 建設業で役員経験2年以上 + 他業種含め役員経験5年以上
- または、役員経験5年以上(うち建設業2年以上)
補佐者の要件:
- 申請会社での勤務経験5年以上
- 財務管理・労務管理・業務運営のいずれかの専門経験5年以上
💡 ここがポイント!
パターンBは、他業種からの参入や事業承継を想定した制度です。
ただし補佐者は「自社での5年以上」が条件なので、新設会社では難しい場合があります。
重要な注意点
- 常勤性が厳しくチェックされます:健康保険被保険者証で証明
- 他社の役員を兼任していると認められません
- 経験は合算可能:個人事業主時代 + 法人役員時代の合算もOK
条件2:技術のプロがいること(営業所技術者等)
2024年12月改正で呼称が変更されました!
従来の「専任技術者」は以下のように変更:
一般建設業:営業所技術者
特定建設業:特定営業所技術者
建設工事の技術面を責任もって管理する人が必要です。
次のうちどれか一つを満たせばOK:
- 国家資格を持っている
- 施工管理技士(1級・2級)
- 建築士(1級・2級)
- 電気工事士
- その他業種に応じた資格
- 学歴 + 実務経験
- 大学・高専の指定学科卒業 → 実務経験3年以上
- 高校の指定学科卒業 → 実務経験5年以上
- 実務経験のみ
- 10年以上の実務経験
条件3:お金の準備ができていること
「しっかりとした資金力」も必要です。
次のうちどちらかを満たせばOK:
- 前年の決算で自己資本が500万円以上ある
- 銀行に500万円以上の預金がある(残高証明書が必要)
💡 ここがポイント!
「自己資本500万円なんて無理…」と思っても、銀行の預金残高で証明できます。
一時的に資金を集めて証明書を取る方法もあるので、諦める必要はありません!
条件4:きちんとした事務所があること
「独立した事務所」が必要です。
要するに:
・自分の建物か、営業用として借りた建物
・他の用途と区別された、建設業専用のスペース
・電話、机、書庫などの事務用品を備えている
自宅の一部でも条件を満たせば大丈夫な場合もあります!
条件5:誠実に仕事をすること
これは「真面目に契約を守る会社かどうか」ということです。
普通に事業をしていれば、まず問題ありません。
条件6:問題のある人がいないこと
最後は「法的に問題のない人たちかどうか」のチェックです。
次のような人がいると許可が取れません:
・破産して復権していない人
・一定期間内に罪を犯した人
・契約で不正をしそうな人
・暴力団関係者
普通の経営をしていれば心配いりませんね。
条件7:適切な社会保険への加入(2020年改正で必須要件化)
2020年10月1日以降、社会保険への適切な加入が許可の絶対的な要件となりました。
対象となる保険:
・健康保険
・厚生年金保険
・雇用保険
加入義務:
法人:原則として全事業所
個人事業主:常時5人以上の従業員を使用する場合
⚠️ 重要!
社会保険に未加入の場合、他の要件を満たしても許可は取得・更新できません。
2024年法改正の重要な変更点
🔧 ICT活用による技術者配置の柔軟化
これまでの常識が変わりました!
一定の条件を満たせば、主任技術者・監理技術者が複数現場を兼任することが可能になりました。
兼任の条件:
- 請負金額:1億円未満(建築一式工事は2億円未満)
- 兼任現場数:2現場以下
- 現場間の移動時間:おおむね2時間以内
- ICTの活用:ウェアラブルカメラ等による遠隔管理システムの導入(必須)
💰 労働者の処遇改善
労務費の適正化が法的に義務化されます
- 中央建設業審議会が「労務費の基準」を策定
- 不当に低い労務費での見積り提出・契約締結が禁止
- 法定福利費の明示が推奨
📋 契約ルールの明確化
資材価格変動への対応が義務化
- 契約書に資材価格変動時の変更方法を明記することが必須
- 「おそれ情報」の事前提供義務
- 発注者・受注者双方の誠実協議義務
申請手続きのデジタル化
🖥️ JCIPシステムの導入
「建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)」が全国で順次開始されています。
利用方法:
・「GビズID」のアカウント取得が必要
・手数料はPay-easy(ペイジー)での電子納付
・添付書類はPDFデータでアップロード
費用はどのくらいかかるの?
💰 建設業許可申請の費用
合計:約25万円
- ・行政への手数料:9万円(知事許可)/15万円(大臣許可)
- ・書類取得費:約1万円
- ・専門家への報酬:約15万円
🔄 更新手続きの費用
合計:約15万円(5年ごと)
- ・行政への手数料:5万円
- ・専門家への報酬:約10万円
🎯 専門家に依頼するメリット
- ・本業に集中できる(慣れない作業で時間を無駄にしない)
- ・面倒な書類取得を全部お任せできる
- ・更新時期の管理もしてもらえる
- ・微妙なケースでも取得できる可能性が高い
どのくらい時間がかかるの?
申請してから許可が下りるまで、約30日〜45日かかります。
準備期間も含めると、トータルで2〜3ヶ月は見ておくと安心ですね。
⏰ 重要!更新のタイミング
建設業許可は5年間有効です。
期限の30日前までに更新手続きが必要なので、早めの準備が大切です!
一人で申請するのは大変?専門家に頼むべき?
正直言うと、建設業許可の申請はかなり複雑です。
こんな作業が必要になります:
- 複雑な申請書類の作成
- 様式第一号から第二十号まで多数の書類
- 2024年改正により様式も変更(営業所技術者等一覧表など)
- 各種証明書の取得
- 住民票、身分証明書、登記事項証明書
- 納税証明書、残高証明書
- 常勤性確認書類(マイナ保険証、健康保険資格確認書など)
- 経営経験・実務経験の詳細な証明
- 過去の確定申告書、工事契約書
- 組織図、業務分掌規程(チーム体制の場合)
- 財産状況の証明
- 決算書、残高証明書の準備
- 社会保険加入状況の確認
- 適切な社会保険への加入証明
- 2024年法改正対応
- ICT活用計画(技術者兼任制度利用の場合)
- 新契約ルールへの対応準備
「自分でやってみたけど挫折した…」という相談をよく受けます😅
✨ 当事務所の特徴
年間1000件以上のご相談をいただいており、これまで許可取得率100%を維持しています。
・LINE相談対応で気軽に質問できる
・夜間・土日相談も可能(要予約)
・お客様のところまで出張相談
・万が一許可が取れなかった場合は全額返金
・取得後のサポートも充実
まとめ:建設業許可は正しい準備で必ず取れます!
建設業許可は確かに複雑ですが、正しく準備すれば必ず取得できます。
大切なのは:
「うちの会社は条件を満たしているかな?」
「申請書類の準備が大変そう…」
そんな不安があれば、まずは気軽にご相談ください。
初回相談は無料ですし、LINEでの相談も可能です!
あなたの建設業許可取得を、心を込めてサポートさせていただきます!
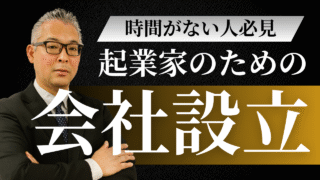

【お問い合わせはこちら】
やさしい行政書士事務所
代表行政書士 宮本 雄介
所在地: 〒257-0003 神奈川県秦野市南矢名2123-1
電話番号: 0463-57-8330 (受付時間:平日9:00~18:00)
メール: info@yusukehoumu.com
ウェブサイト: https://yusukehoumu.com/
▼LINEでのお問い合わせも可能です!▼
LINEで無料相談を予約する
初回相談は無料です。オンライン相談、夜間・土日相談(要予約)、訪問相談も承ります。お気軽にご連絡ください。
<<<TOPページへ>>>
◆お問合せフォーム
お問い合わせ内容は、公開されません。
安心してご記入ください。