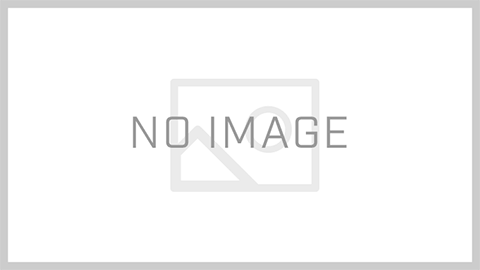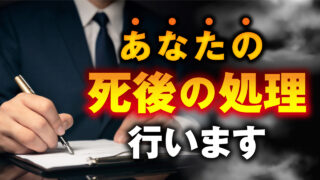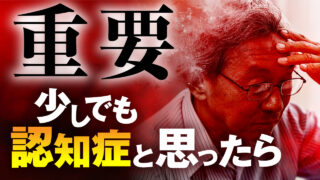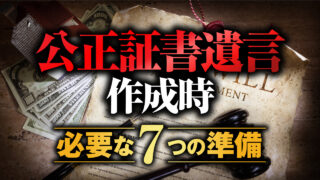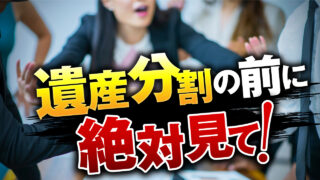人手不足で悩んでいませんか?「外国人を雇いたいけど、手続きが複雑そう…」「ビザのことがよく分からない…」そんな不安を抱えている経営者の方、人事担当者の方も多いと思います。
確かに外国人雇用には、日本人を雇う時とは違う特別なルールや手続きがあります。でも、正しい知識を身につければ、決して難しいものではありません。
この記事では、外国人雇用の「分からない」を「分かった!」に変える情報をお届けします。1000件以上の外国人関連のご相談にお答えしてきた行政書士が、専門用語を使わずに、分かりやすく解説していきますね。
目次
👥外国人労働者の募集方法
まずは外国人の方をどうやって見つけるかです。主な方法は3つあります:
- 求人サイト・SNS:インターネットを使って幅広く募集
- 知人の紹介:外国人コミュニティとつながりがある人に頼む
- 人材紹介会社:専門の会社に依頼(手数料は年収の20~30%が相場)
💡 ワンポイント
人材紹介会社を利用する場合は、「登録支援機関」として認定されている会社を選ぶと安心です。外国人の受け入れに詳しく、手続きもスムーズに進みます。
📋外国人雇用を始める前に!知っておきたい重要なこと
誰でも雇えるの?在留資格(ビザ)の基本ルール
実は、外国人だからといって誰でも自由に日本で働けるわけではないんです。「在留資格」という許可が必要で、その内容によって働ける仕事が決まっています。
よく「就労ビザ」と言いますが、正式には「在留資格」と呼びます。これを理解することが外国人雇用の第一歩です。
在留資格は3つのグループに分かれます
① 何でも働けるグループ
- 永住者
- 日本人の配偶者等
- 定住者など
→ 日本人とほぼ同じ扱いで、どんな職種でも働けます
② 決められた仕事だけ働けるグループ
- 技術・人文知識・国際業務(IT関係、事務系、通訳など)
- 技能(料理人、建築技術者など)
- 特定技能(介護、建設、農業など16分野)
- 経営・管理(会社経営者など)
→ 許可された範囲の仕事のみ
③ 基本的に働けないグループ
- 留学生(週28時間以内のアルバイトは許可があればOK)
- 家族滞在
- 観光客など
⚠️ 重要な注意点
受け入れの準備と心構え
外国人雇用を成功させるには、事前の準備が大切です。特に以下の点を考えておきましょう:
💰 コストの把握
- 人材紹介会社への手数料
- 在留資格申請の費用(行政書士報酬など)
- 海外から来る場合の渡航費支援
- 日本語教育や研修費用
🏢 社内体制の整備
- 外国人従業員をサポートする担当者を決める
- 配属先の部署に外国人受け入れについて説明する
- 重要な書類は英語版も用意する
- 困ったときの相談窓口を作る
🤝 異文化理解
- 文化や習慣の違いを認識し、尊重する
- 「やさしい日本語」でゆっくり、はっきり話す
- 宗教的な配慮(イスラム教の礼拝時間など)
- 翻訳ツールやジェスチャーの活用
💡 長期的な視点を持ちましょう
外国人雇用は短期的な労働力確保だけでなく、長期的な人材育成の観点で考えることが成功のカギです。1000件以上のご相談を受けた経験から言えるのは、しっかりとサポートした企業ほど、優秀な外国人材に長く働いてもらえているということです。
📝【ケース別】外国人雇用の手続き完全ガイド
外国人雇用の手続きは、採用する方が海外にいるか、すでに日本にいるかで大きく変わります。それぞれのパターンを見てみましょう。
【パターン1】海外在住者を採用する場合
海外から外国人を呼び寄せる場合の流れです:
- 募集・選考・内定
海外の求人サイトや人材紹介会社を活用して候補者を見つけます - 雇用契約の締結
労働条件を明確にした契約書を作成(英語版もあると良いです) - 在留資格認定証明書(COE)の申請【重要!】
これが一番重要な手続きです。「この外国人は日本で働いてOKです」という証明書を入管に申請します - COEを本人に送付
許可が出たら海外にいる本人に郵送します - 本人がビザ申請
現地の日本大使館でビザを取得してもらいます - 来日・入社
COEの有効期間(3ヶ月)内に来日し、住民登録などの手続きを行います
💡 専門家のサポートをおすすめします
【パターン2】国内在住者を採用する場合
すでに日本にいる外国人(他社で働いている方、留学生など)を採用する場合:
- 募集・選考・内定
重要: 必ず在留カードの原本で以下を確認- 在留資格の種類
- 在留期限
- 就労制限の有無
- 雇用契約の締結
- 在留資格変更申請(必要な場合)
留学生を正社員で雇う場合や、転職で仕事内容が変わる場合は変更申請が必要です - 入社
変更許可が出てから(または変更が不要な場合はそのまま)入社
⚠️ 留学生採用の注意点
📄在留資格(ビザ)を分かりやすく解説
主要な就労可能在留資格
企業でよく使われる在留資格をピックアップして説明しますね:
🔧 技術・人文知識・国際業務
対象の仕事:
- 技術系:SE、システム開発、設計など
- 人文知識系:企画、営業、経理、事務など
- 国際業務系:通訳、翻訳、海外取引、語学指導など
主な条件: 大学卒業程度の学歴、または関連する実務経験(国際業務は3年、その他は10年)
🍳 技能
対象の仕事: 外国料理の調理師、建築技術者、パイロット、スポーツ指導者など
主な条件: それぞれの分野で定められた実務経験(調理師なら10年など)
⚙️ 特定技能
対象の仕事: 介護、建設、農業、宿泊、外食など16分野
主な条件: 分野別の技能試験と日本語試験に合格、または技能実習2号を修了
💼 経営・管理
対象の仕事: 会社経営、事業管理
主な条件: 事業所の確保、資本金500万円以上または常勤職員2名以上雇用
申請でよくある失敗と成功のコツ
❌ よくある失敗例
- 書類の不備や記載ミス
- 業務内容と在留資格の不一致
- 学歴・職歴の証明不足
- 雇用理由の説明不足
- 会社の安定性への懸念
✅ 成功のコツ
- 在留資格の趣旨と審査基準を理解する
- すべての書類に整合性を持たせる
- 「なぜこの人が必要なのか」を具体的に説明する
- 客観的な資料で要件を満たしていることを証明する
- 分かりやすい文章で書く(専門用語を避ける)
💡 専門家に相談するメリット
当事務所では、単に書類の形式を整えるだけでなく、「なぜこの方を採用したいのか」「この方の能力がどう活かされるのか」といった「ストーリー」を構築することを重視しています。
分かりやすい理由書の作成に特に力を入れており、審査官にスムーズに理解してもらえる書類作りを得意としています。
⚖️失敗しないための法的注意点
不法就労の防止策
外国人雇用で最も気をつけなければならないのが「不法就労」です。以下の場合は違法になります:
- 在留カードの原本提示(コピー不可)
- 有効期限の確認
- 在留資格の種類
- 就労制限の有無
- 留学生の場合は資格外活動許可の有無
労働条件・社会保険・税金
外国人だからといって特別扱いはできません。日本人と同じルールが適用されます:
- 労働基準法:労働時間、休憩、有給休暇、最低賃金など
- 社会保険:健康保険、厚生年金(条件を満たせば加入義務)
- 労働保険:雇用保険、労災保険
- 税金:所得税、住民税の源泉徴収
💡 トラブル防止のために
雇用契約書や就業規則は、可能な限り外国人の方が理解できる言語(英語や母国語)でも用意することをおすすめします。厚生労働省が多言語のモデル様式を提供しているので活用しましょう。
🤝採用後の定着支援のポイント
コミュニケーションと環境づくり
外国人材に長く働いてもらうためには、採用後のサポートが重要です:
🗣️ 言語サポート
- 必要に応じて日本語研修の機会提供
- 「やさしい日本語」での会話(短い文、簡単な言葉)
- 翻訳ツールの活用
- 重要な情報の多言語化
🌍 異文化理解
- お互いの文化を理解する研修
- 交流会や懇親会の開催
- メンター制度の導入
- 宗教的配慮(礼拝時間、食事制限など)
🏠 生活面のサポート
- 住居探しの支援
- 銀行口座開設の同行
- 役所手続きのサポート
- 生活ルールの説明
💡 当事務所からのアドバイス
多くの企業様から「言葉の壁」や「文化の違いによる誤解」についてご相談をいただきます。大切なのは、一方的に日本のやり方を押し付けるのではなく、お互いの違いを理解し合うこと。ちょっとした配慮やコミュニケーションの工夫で、関係は大きく改善します。
当事務所では、異文化理解に関する情報提供やアドバイスも行っています。
🎯まとめ
外国人雇用は確かに複雑な面もありますが、適切な知識と準備があれば、企業にとって大きな戦力となります。人手不足の解消だけでなく、多様性による新たなアイデアや成長機会も期待できるでしょう。
重要なのは以下の3点です:
- 事前準備をしっかりと
在留資格の理解、社内体制の整備、コストの把握 - 正確な手続き
書類不備や判断ミスは大きなリスクに - 継続的なサポート
採用後の定着支援が成功の鍵
🏢 やさしい行政書士事務所について
私たちは1000件以上の外国人関連のご相談にお答えしてきました。在留資格申請を得意分野とし、AIツールも活用した効率的で正確な手続きを提供しています。
当事務所の特長:
💰 料金例(税別)
| 手続き内容 | 費用 |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請 | ¥99,800 |
| 在留資格変更許可申請 | ¥99,800 |
| 就労資格証明書交付申請 | ¥99,800 |
| 在留資格更新許可申請 | ¥49,800 |
外国人雇用でお悩みの方、まずはお気軽にご相談ください。適切な手続きを踏めば、きっと素晴らしい人材との出会いが待っています。
一緒に御社の成長をサポートさせていただきます!
【お問い合わせはこちら】
やさしい行政書士事務所
代表行政書士 宮本 雄介
所在地: 〒257-0003 神奈川県秦野市南矢名2123-1
電話番号: 0463-57-8330 (受付時間:平日9:00~18:00)
メール: info@yusukehoumu.com
ウェブサイト: https://yusukehoumu.com/
▼LINEでのお問い合わせも可能です!▼
LINEで無料相談を予約する
初回相談は無料です。オンライン相談、夜間・土日相談(要予約)、訪問相談も承ります。お気軽にご連絡ください。
<<<TOPページへ>>>
◆お問合せフォーム
お問い合わせ内容は、公開されません。
安心してご記入ください。