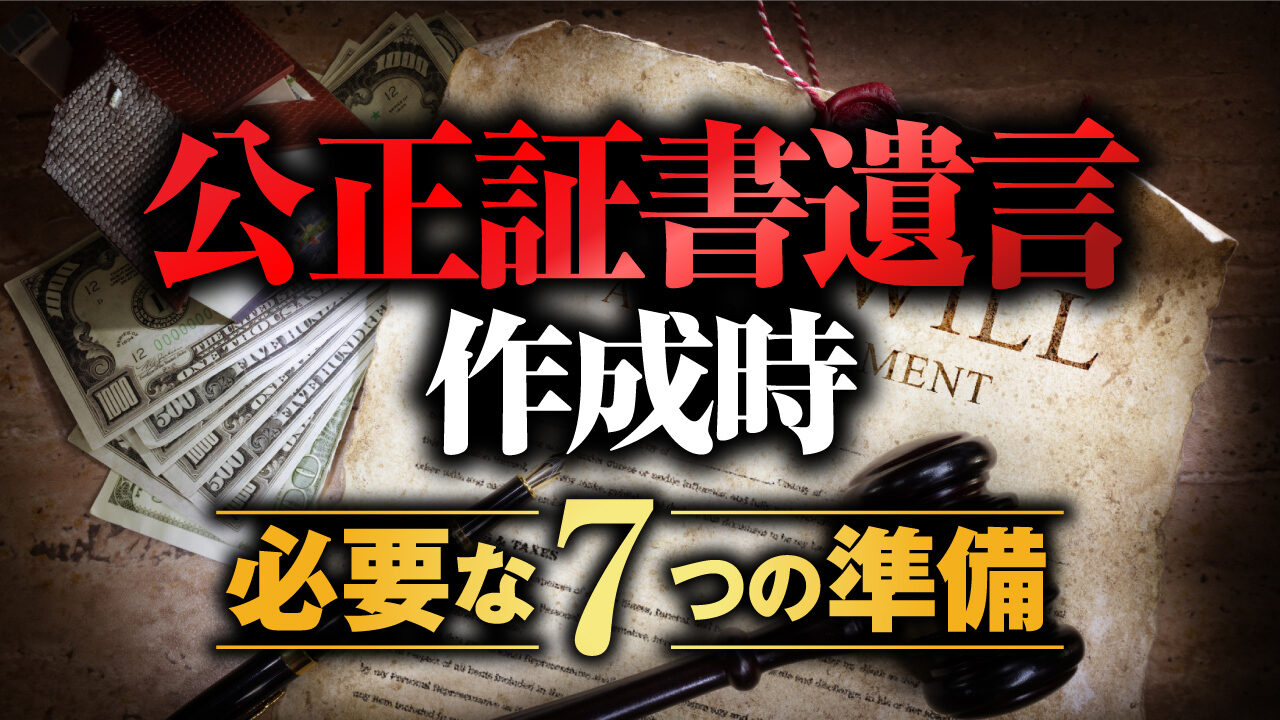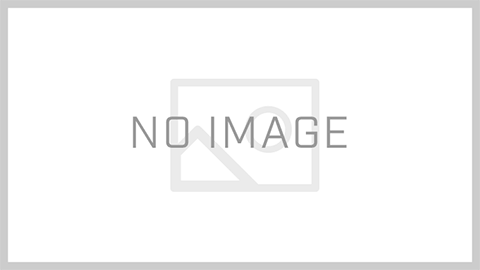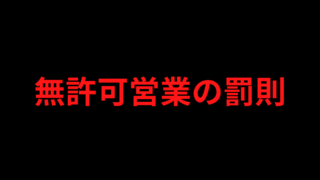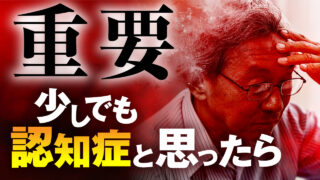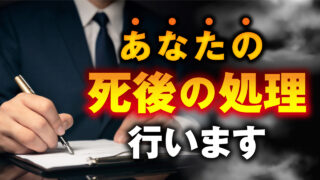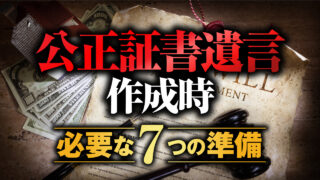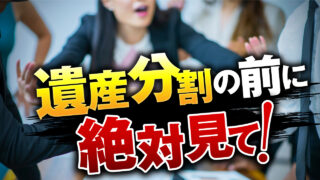将来の相続トラブルを防ぎ、大切なご家族へ想いを確実に伝えるために「遺言書」の作成を考える方が増えています。中でも、公証人が作成に関与する「公正証書遺言」は、その確実性や信頼性の高さから注目されています。しかし、「具体的にどうやって作るの?」「費用は?」「自筆証書遺言とどう違うの?」といった疑問や、「手続きが難しそう」「誰に相談すればいいの?」といった不安をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
この記事では、相続・遺言手続きで1000件以上の相談実績を持つ「やさしい行政書士事務所」が、公正証書遺言の基本から作成のステップ、費用、必要書類、注意点、そして専門家である行政書士に依頼するメリットまで、網羅的に解説します。特に、行政書士への依頼を検討されている方に向けて、当事務所ならではのサポート体制や考え方についても触れていきます。この記事を読めば、公正証書遺言に関するあなたの疑問や不安が解消されるはずです。
目次
公正証書遺言とは?
公正証書遺言は、遺言の中でも特に信頼性が高い形式です。ここでは、その定義や法的な効力、なぜ「確実」と言われるのか、そして最も比較される自筆証書遺言との違いを、メリット・デメリットを交えながら分かりやすく解説します。遺言形式選びの第一歩として、基本をしっかり押さえましょう。
公正証書遺言と法的効力
公正証書遺言とは、遺言者(遺言を残す人)が、公証人(法律の専門家)と証人2名以上の立会いのもとで遺言の内容を伝え、公証人がそれを文書化して作成する遺言書のことを指します(民法第969条)。
公証人は、元裁判官や検察官など法律実務の経験が豊富な専門家であり、全国の公証役場に在籍しています。
公正証書遺言には、主に以下のような法的な効力があります。
- 相続分の指定:法定相続分とは異なる割合で相続分を指定できます。
- 遺産分割方法の指定:「不動産は長男に、預貯金は次男に」など、具体的な分割方法を指定できます。
- 遺贈:相続人以外の人や団体(お世話になった人、NPO法人など)に財産を渡すことができます。
- 子の認知:婚姻関係にない男女間に生まれた子を自分の子として認知できます。
- 未成年後見人の指定:親権者がいなくなる場合に備え、未成年者の子の後見人を指定できます。
- 遺言執行者の指定:遺言の内容を実現する手続きを行う遺言執行者を指定できます。
では、なぜ公正証書遺言は「確実」と言われるのでしょうか?その理由は主に以下の3点にあります。
- 公証人による内容・形式チェック:法律の専門家である公証人が、遺言者の意思を確認しながら、法律的に有効な形式で遺言書を作成します。そのため、自筆証書遺言で起こりがちな形式不備(日付の記載漏れ、署名押印漏れなど)による無効のリスクが極めて低くなります。
- 原本の公証役場保管:作成された公正証書遺言の原本は、原則として遺言者が120歳になるまで公証役場で厳重に保管されます。これにより、遺言書の紛失、盗難、偽造、変造、相続人による隠匿や破棄といったリスクを防ぐことができます。万が一、遺言者に渡された正本や謄本を紛失しても、公証役場で再発行が可能です。
- 家庭裁判所の検認が不要:自筆証書遺言の場合、遺言者の死後、家庭裁判所で「検認」という手続きが必要になります。これは遺言書の偽造や変造を防ぐための手続きですが、時間と手間がかかります。一方、公正証書遺言は公証人が作成に関与しているため、この検認手続きが不要です。これにより、相続開始後、よりスムーズに遺言の内容を実現する手続き(不動産の名義変更や預貯金の解約など)を進めることができます。
💡ワンポイント
当事務所では、これまで数多くの相続手続きに関わってまいりましたが、残念ながら遺言書の形式不備で無効になってしまったり、遺言書の有効性を巡って相続人間で争いになったりするケースも見てきました。公正証書遺言は、作成時に費用や手間がかかる側面はありますが、こうした将来のトラブルリスクを大幅に軽減し、遺言者の最終意思を最も確実に実現できる方法の一つと考えています。特に、相続財産が多い方、相続関係が複雑な方、ご自身の意思を確実に残したいと強く願う方には、公正証書遺言の作成を推奨しております。
問い合わせ先(初回無料相談)
電話0463-57-8330
(平日9:00〜18:00)
料金表はこちら
自筆証書遺言との違いは?メリット・デメリット徹底解説
遺言書にはいくつかの形式がありますが、最も一般的なのが「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」です。どちらを選ぶべきか迷う方も多いでしょう。ここでは、両者の主な違いを表で比較し、それぞれのメリット・デメリットを解説します。
| 項目 | 公正証書遺言 | 自筆証書遺言 |
|---|---|---|
| 作成者 | 公証人(遺言者の口授に基づき作成) | 遺言者本人(全文・日付・氏名を自書、押印 ※財産目録はPC作成可) |
| 証人 | 原則2名以上必要 | 不要 |
| 費用 | 公証人手数料等が必要(財産額による) | 原則無料(法務局保管制度利用時は3,900円) |
| 手間・時間 | 公証人との打合せ、証人手配などが必要 | 比較的少ない(いつでも作成可能) |
| 保管 | 公証役場で原本保管 | 自己保管 または 法務局保管制度利用 |
| 検認(家庭裁判所) | 不要 | 必要(法務局保管制度利用時を除く) |
| 無効リスク | 極めて低い | 要件不備(日付・署名漏れ、代筆等)による無効リスクあり |
| 偽造・変造・紛失リスク | 極めて低い(原本は公証役場保管) | リスクあり(特に自己保管の場合) |
| プライバシー | 証人・公証人に内容が知られる | 秘密にしやすい(保管制度利用時は内容確認なし) |
| 代筆 | 口授できれば字が書けなくても可能 | 不可(財産目録除く) |
【公正証書遺言のメリット・デメリット】
- メリット:形式不備による無効リスクがほぼない、偽造・紛失等のリスクがない、検認不要で相続手続きが早い、字が書けなくても作成可能、証明力が高い。
- デメリット:費用がかかる、作成に手間がかかる(公証人との打合せ等)、証人が2名必要、証人等に内容を知られる。
【自筆証書遺言のメリット・デメリット】
- メリット:費用がほぼかからない、いつでも手軽に作成・修正できる、内容を秘密にできる。
- デメリット:形式不備で無効になるリスクがある、偽造・紛失・隠匿のリスクがある(自己保管の場合)、原則として検認が必要で手続きに時間がかかる、内容が不明確だと解釈で争いになる可能性。
【どちらを選ぶべきか?】
どちらの形式が良いかは、個々の状況によって異なります。例えば、以下のような場合は公正証書遺言を検討する価値が高いでしょう。
- 相続財産が高額または種類が多い
- 相続人の関係が複雑で、将来トラブルになる可能性がある
- 確実に遺言の内容を実現したい
- 病気や高齢で字を書くのが難しい
- 検認手続きの手間を相続人にかけたくない
一方、費用を抑えたい、手軽に作成したい、内容を誰にも知られたくないという場合は、自筆証書遺言(特に法務局保管制度の利用)も選択肢となります。ただし、無効リスクや紛失リスクには注意が必要です。
💡ワンポイント
当事務所では、お客様のご意向、ご家族構成、財産状況などを丁寧にお伺いした上で、それぞれの遺言形式のメリット・デメリットを具体的にご説明し、お客様にとって最適な方法をご提案いたします。もちろん、最終的にどの形式を選ばれるかはお客様ご自身ですが、将来の確実性や相続手続きの円滑さを重視される場合には、公正証書遺言をお勧めすることが多いです。自筆証書遺言を選択される場合でも、法務局保管制度の利用を含め、有効な遺言書となるようサポートいたします。
問い合わせ先(初回無料相談)
電話0463-57-8330
(平日9:00〜18:00)
料金表はこちら
公正証書遺言を作成するメリット・デメリット
公正証書遺言には多くのメリットがありますが、一方でデメリットや注意点も存在します。ここでは、メリットを最大限に活かし、デメリットを最小限に抑えるためのポイントを解説します。ご自身の状況に合わせて、公正証書遺言が最適かどうか判断する材料にしてください。
公正証書遺言を選ぶべき5つのメリット
公正証書遺言には多くの利点がありますが、特に相続トラブルの防止や手続きの円滑化という観点から、以下の5つのメリットは非常に大きいと言えます。
- 方式不備による無効リスクがほぼない:
自筆証書遺言では、日付の書き忘れ、押印漏れ、全文自書の要件を満たさないなど、わずかな形式不備で遺言全体が無効になってしまうことがあります。公正証書遺言では、法律の専門家である公証人が作成に関与し、民法の定める方式に従って作成するため、このような形式上の理由で無効になる心配はまずありません。遺言者の意思を確実に法的な効力のあるものとして残せます。 - 偽造・変造・紛失・隠匿のリスクがない:
公正証書遺言の原本は公証役場に厳重に保管されます。そのため、遺言者が亡くなった後に、相続人の誰かが遺言書を破棄したり、自分に都合の良いように書き換えたり(偽造・変造)、あるいは遺言書を紛失してしまうといったリスクがありません。遺言者の真意が確実に保護されます。 - 家庭裁判所の検認が不要で相続手続きがスムーズ:
前述の通り、公正証書遺言は家庭裁判所での検認手続きが不要です。検認は、申立てから手続き完了まで1~2ヶ月程度かかることもあり、その間は相続手続き(預貯金の解約や不動産の名義変更など)を進めることができません。検認が不要な公正証書遺言なら、相続開始後、速やかに相続手続きを開始でき、相続人の負担を軽減できます。 - 本人の意思能力が確認されるため後日の争いを防ぎやすい:
公正証書遺言の作成にあたっては、公証人が遺言者本人と面談し、遺言者に十分な判断能力(遺言能力)があるか、遺言内容が本人の真意に基づくものかを確認します。これにより、後になって「遺言者は認知症で判断能力がなかった」「無理やり書かされたのではないか」といった主張が出され、遺言の有効性が争われるリスクを低減できます。 - 口がきけない人、字が書けない人でも作成可能:
自筆証書遺言は、原則として全文を自分で書かなければなりませんが、公正証書遺言は、遺言者が公証人に遺言の内容を口頭で伝え(口授)、公証人がそれを筆記する形で作成します。そのため、病気や障害などで字を書くことが難しい方でも作成が可能です。また、耳が聞こえない方や口がきけない方でも、通訳などを介して意思を伝えることで作成できます。
💡ワンポイント
当事務所がこれまでサポートさせていただいたお客様の中にも、「まさか自分の家族が相続で揉めるとは思わなかった」とおっしゃる方が少なくありません。相続財産に分割しにくい不動産が多く含まれるケースや、相続人同士の関係があまり良好でないケース、前妻の子と後妻の子がいるケースなどでは、公正証書遺言の持つ「証明力の高さ」と「検認不要」というメリットが特に重要になります。実際に、公正証書遺言があったおかげで、複雑な相続案件でも驚くほどスムーズに手続きが進み、ご遺族の負担を大きく軽減できた事例を数多く経験しています。
問い合わせ先(初回無料相談)
電話0463-57-8330
(平日9:00〜18:00)
料金表はこちら
知っておくべきデメリットと対策
多くのメリットがある公正証書遺言ですが、デメリットや注意点も理解しておく必要があります。主なデメリットとその対策について解説します。
- 費用がかかる:
公正証書遺言の作成には、公証人に支払う手数料が必要です。手数料は、遺言書に記載される財産の価額に応じて計算され、財産額が大きいほど高くなります。また、必要書類の取得費用や、行政書士などの専門家に依頼する場合はその報酬もかかります。
【対策】費用はかかりますが、将来の相続トラブルを防止できる効果や、検認手続きが不要になることによる相続人の負担軽減を考えれば、費用対効果は高いと言えます。事前に公証役場や専門家に見積もりを依頼し、総額を確認しておくと安心です。 - 作成に手間と時間がかかる:
自筆証書遺言のように思い立った時にすぐ作成できるわけではありません。事前に遺言内容を検討し、必要書類を収集し、公証役場に予約を入れて公証人と打ち合わせを行い、証人を手配するなど、一定の手順を踏む必要があり、完成までに数週間から1ヶ月以上かかることもあります。
【対策】行政書士などの専門家に依頼すれば、必要書類の収集代行、公証人との打ち合わせ調整、遺言内容の整理などを任せることができ、ご自身の負担を大幅に軽減できます。 - 証人が2名必要:
公正証書遺言の作成には、信頼できる証人2名以上の立会いが必要です。証人には欠格事由(後述)があり、誰でもなれるわけではありません。また、遺言の内容を証人に知られることになります。
【対策】証人の要件を満たす信頼できる友人や知人に依頼する方法がありますが、適当な人が見つからない場合や、知人に内容を知られたくない場合は、行政書士や弁護士などの専門家や、公証役場で紹介してもらえる証人に依頼することができます(別途費用がかかる場合あり)。専門家は守秘義務を負っているため、プライバシーの面でも安心です。 - 遺言内容が証人や公証人に知られる:
作成プロセス上、遺言の内容は公証人と証人に知られることになります。秘密にしておきたい内容がある場合にはデメリットと感じるかもしれません。
【対策】公証人や行政書士などの専門家には厳格な守秘義務が課せられていますので、遺言の内容が外部に漏れる心配は基本的にありません。どうしても内容を秘密にしたい場合は、秘密証書遺言という別の形式もありますが、手続きが複雑で利用されるケースは稀です。
💡ワンポイント
「費用がどれくらいかかるか心配」「証人になってくれる人が周りにいない」「手続きが面倒そう」といったお悩みは、私たちが解決します。当事務所では、初回のご相談時に、かかる費用の概算と内訳を分かりやすくご説明し、ご納得いただいた上で業務に着手いたしますのでご安心ください。証人の手配についても、守秘義務を遵守する信頼できる証人をご用意することが可能です。また、必要書類の収集から公証人との連絡調整、遺言書案の作成サポートまで、お客様のご負担を最小限にするための包括的なサポートを提供しております。お忙しい方でもスムーズに公正証書遺言を作成できるよう、全力でお手伝いいたします。
問い合わせ先(初回無料相談)
電話0463-57-8330
(平日9:00〜18:00)
料金表はこちら
【完全ガイド】公正証書遺言の作成手順と流れ
公正証書遺言を作成したいと思っても、具体的に何から始め、どのような手順で進めればよいのか分からない方も多いでしょう。ここでは、遺言内容の検討から公証役場での作成完了までの具体的なステップを、必要な準備物とともに詳しく解説します。
公正証書遺言作成時に必要な7つの準備
まず先に言っておきたいのは、よく遺言書を自分で書いてから公証役場に行かれる方も結構いらっしゃいます。
ただ実際に遺言の中身というのは公証人の先生がまとめてくれるので、簡単なもので大丈夫です。
Excelでまとめた表でもいいくらいです。
本当に必要なのは必要書類の方なんですね。
そっちが揃わないと先に進めないということで、以下の表にしてみました。
| 1.遺言者本人の印鑑登録証明書1通 | これは本人確認のためです。公正証書作成当日には、実印も持参してください。 「実印自体を作ってない」 「いっぱい印鑑あって どれが実印か忘れた」 という方も安心してください。 パスポートや免許証と、認印でもOKです。 |
| 2.戸籍謄本(相続人全員記載) | 相続人全員が記載されているものが 必要になります。 戸籍謄本は本籍地で取る必要があります。 役所の担当者に「相続人全員が記載された 戸籍謄本をください」といえば、だいたい揃うのですが、相続人が結婚してたりすると、転籍後の本籍地の役所まで取りに行かないと行けなくなります。 |
| 3.親・子・配偶者・兄妹以外の人に財産をあげる場合、これを貰う人の住民票1通 | 法定相続人以外の第三者を特定する場合には、「氏名、住所、生年月日」この3つで特定するんです。 この3つを特定するために住民票が必要になります。 代わりになるものとしては、その人の運転免許証の写しとか、保険証の写しとかでも特定できることはできます。 ですが、その人に知られないようにしたいという方もいらっしゃいますよね。 例えば、遠い親戚に相続財産の一部をあげたいとかの場合。そういう時は、続柄で特定することもできます。 自分の兄弟の子供の奥さんとかですね。 あとは法人にあげる場合、そういう時は、 名称と本店所在地が必要なので、登記情報を取ってもらったりすることも必要です。 |
| 4.不動産を相続させる場合、不動産登記簿謄本1通と固定資産評価証明書1通 | あげる財産を特定するための資料になります。 1戸建の場合、ご自宅にある 「固定資産課税通知書に同封の課税明細書」でも代用できます。 建物があって、その敷地利用権が賃借権の場合、その賃借権を財産として書くことになるので、その賃貸借契約書の写しが必要になります。 あと、建築中の建物がある場合、請負契約の注文者の地位があるのでそれを相続させることになります。 建物が完成したらその建物を相続させると 書けば良いなので、請負契約書の写しがあれば遺言に書くことができます。 ちなみに不動産の中の家具などもどのようにするか指定しておかないと、相続人全員の共有物になり、不動産を取得した人が勝手に処分できなくなるので注意が必要です。 |
| 5.その他、預貯金などを相続させる場合 | 基本的には通帳の写しを持っていきますが、 銀行名・支店名・預金種別・口座番号か証書番号のメモでもOKです。 少なくとも銀行名・支店名が必要です。 証券会社に預けた株式とかを、証券会社にある財産という形でとひっくるめるのであるならば、証券会社の名称だけわかっていればそれを相続させることもできます。 証券会社の場合、定期的に報告書が発行されていると思いますが、その報告書を確認資料として使えます。 非上場会社のオーナー会社の場合、そういう時は、名称と本店所在地で特定するので、登記情報それから発行株数と遺言者が持っている株数の確認資料として、法人税申告書の株の部分が記載されている箇所の写し 法人税申告書に添付してある貸借対照表の純資本の部が記載されている箇所の写し 生命保険の場合は、受取人がはっきり決まっていれば遺言に書かなくてもOKです。契約者は遺言者だけど、被保険者は別の人とかの場合、契約者・被保険者・受取人が遺言者の場合、こういう場合は遺言書いた方が良いです。 保険証書が確認資料になります。 その他、宝石、金地金、毛皮、絵画、とか遺言にすることもできますが、特定する方法には工夫が必要です。これは個別にご相談ください。 |
| 6.遺言執行者を決めておくこと | 遺言通りに手続きを実行する人の事です。配偶者、子孫、その財産を貰う人でもOKです。 |
| 7.公正証書作成時には証人が2名必要 | 親族以外の人2名選び、住所・氏名・生年月日・職業をメモでいいので書いてください。 ただ欠格事由のある人は証人にはなれません。 将来問題が起きない方を選ぶ必要があります。 |
ステップ解説①:遺言内容の検討から必要書類の準備まで
公正証書遺言の作成は、しっかりとした準備から始まります。主に以下のステップで進めていきます。
- 遺言内容の検討・決定:
まず、誰に(相続人、受遺者)、どの財産を、どのくらいの割合で残したいのかを具体的に考えます。法定相続分通りにするのか、特定の相続人に多く渡したいのか、相続人以外の人にも財産を遺贈したいのかなどを明確にします。また、財産分与だけでなく、感謝の言葉や遺言を作成した理由などを記す「付言事項」も盛り込むことができます。これは法的な効力はありませんが、相続人に遺言者の想いを伝え、円満な相続に繋がることもあります。 - 財産目録の作成:
遺言書に記載する財産を正確に把握し、リスト化(財産目録を作成)します。不動産(土地・建物)、預貯金、有価証券(株式、投資信託など)、生命保険金、自動車、貴金属、骨董品、貸付金など、プラスの財産だけでなく、借金やローンなどのマイナスの財産も記載します。不動産は登記簿謄本(登記事項証明書)の記載通りに、預貯金は金融機関名・支店名・口座番号などを正確に記載する必要があります。 - 相続人の確定:
誰が法的な相続人となるのかを確定します。遺言者の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)等を取得し、相続関係を正確に把握します。 - 必要書類の収集:
前項の表「公正証書遺言作成時に必要な7つの準備」を参考に必要書類を収集してください。
💡ワンポイント
「何をどう書けばいいか分からない」「財産のリストアップが大変」「戸籍謄本を集めるのが面倒」…遺言書の準備段階は、多くの方がつまずきやすいポイントです。当事務所では、お客様の想いを形にするための遺言内容の整理から、正確な財産目録の作成、複雑な戸籍謄本の収集代行まで、トータルでサポートいたします。
特に、外国人の方の場合、相続財産が国内外に渡っていたり、本国の身分関係書類が必要になったりと、手続きがより複雑になる傾向があります。当事務所は在留資格(ビザ)申請の専門家でもあり、外国人の方特有の手続きにも精通しておりますので、安心してお任せください。また、経営者の方には、会社の株式や事業用資産の承継についても、事業承継計画と連携させながら最適な遺言内容をご提案することが可能です。
問い合わせ先(初回無料相談)
電話0463-57-8330
(平日9:00〜18:00)
料金表はこちら
ステップ解説②:公証役場との連携と当日の流れ
必要書類が揃い、遺言内容の原案が固まったら、いよいよ公証役場での手続きに進みます。
- 公証役場の選定・予約:
原則として、どこの公証役場でも作成可能ですが、アクセスしやすい場所や、相談しやすい公証人がいる役場を選ぶと良いでしょう。事前に電話などで連絡し、公正証書遺言を作成したい旨を伝え、相談・作成の日時を予約します。 - 公証人との打ち合わせ:
予約した日時に公証役場へ行き、公証人と打ち合わせを行います。作成した遺言内容の原案や収集した必要書類を提出し、遺言者の意思や財産状況などを詳しく説明します。公証人は、内容が法的に問題ないか、遺言者の意思が明確かなどを確認し、必要に応じて修正案などを提示します。打ち合わせは1回で終わることもありますが、内容が複雑な場合は複数回行うこともあります。 - 遺言公正証書(案)の確認・修正:
打ち合わせに基づき、公証人が遺言公正証書の案を作成します。案が完成したら、遺言者に提示(郵送やメールの場合もあり)されるので、内容に間違いがないか、自分の意図通りになっているかを慎重に確認します。修正したい点があれば公証人に伝え、最終的な内容を確定させます。 - 証人の手配・確定:
作成当日に立ち会ってもらう証人2名以上を手配します。自分で依頼する場合は、事前に証人予定者の氏名、住所、生年月日、職業などを公証人に伝えます。専門家や公証役場に紹介を依頼する場合は、その旨を伝えます。- 公証役場での作成当日:
指定された日時に、遺言者と証人2名以上が公証役場に出向きます(実印、本人確認書類を持参)。当日の流れは概ね以下の通りです。 - ステップ1 遺言者、証人2名以上、公証人が同席します。
- ステップ2 遺言者が、証人の面前で、公証人に遺言の内容を口頭で伝えます(口授)。事前に打ち合わせした内容と同じであることを確認する形が一般的です。
- ステップ3 公証人が、遺言者の口授した内容を筆記し、遺言公正証書を作成します。(実際には事前に作成された案を確認する形が多いです)
- ステップ4 公証人が、作成した証書の内容を遺言者と証人に読み聞かせるか、閲覧させます。
- ステップ5 遺言者と証人は、筆記の内容が正確であることを確認した後、それぞれ署名し、実印(遺言者)または認印(証人)を押印します。
- ステップ6 公証人が、証書が民法の定める方式に従って作成されたものである旨を付記し、署名・押印します。
- ステップ7 公正証書遺言が完成します。遺言者は公証人手数料を支払い、遺言書の正本と謄本を受け取ります(原本は公証役場で保管)。
- 公証役場での作成当日:
- 出張作成について:
遺言者が病気や高齢などの理由で公証役場に出向くことが難しい場合は、公証人に自宅や病院、施設などに出張してもらい、遺言書を作成することも可能です(別途、日当や交通費がかかります)。
💡ワンポイント
「公証役場に行くのが不安」「手続きに同席してほしい」という方もご安心ください。当事務所では、公証人との打ち合わせへの同行はもちろん、作成当日の立会い(証人として、または証人とは別にサポート役として)も行っております。お客様が安心して手続きに臨めるよう、専門家として隣でサポートいたします。
また、ご高齢の方やお身体が不自由な方で、公証役場への訪問が困難な場合には、ご自宅や入所施設への訪問相談も積極的に承っております。必要であれば、公証人の出張作成の手配もサポートいたします。ご多忙な方のために、LINEでの事前打ち合わせや、土日祝・夜間(事前予約制)の対応も可能です。お客様のご都合に最大限合わせた柔軟なサポート体制を整えていますので、まずはお気軽にご相談ください。
▼LINEでのお問い合わせも可能です!▼
LINEで無料相談を予約する
問い合わせ先(初回無料相談)
電話0463-57-8330
(平日9:00〜18:00)
料金表はこちら
公正証書遺言の「証人」と「費用」
公正証書遺言の作成において、多くの方が疑問に思うのが「証人」と「費用」についてです。誰が証人になれるのか、どうやって探せばいいのか、費用は総額でいくらくらいかかるのか。ここでは、これらの疑問に具体的にお答えします。
証人は誰に頼む?なれない人は?
公正証書遺言の作成には、証人2名以上の立会いが法律で義務付けられています(民法第969条1号)。証人は、遺言者が本人の意思で遺言内容を話し、手続きが適正に行われたこと証明する重要な役割を担います。
【証人になれない人(欠格者)】
誰でも証人になれるわけではなく、以下の人は証人になることができません(民法第974条)。これらの欠格者が証人となった場合、遺言が無効になる可能性があるため注意が必要です。
| 欠格者となる対象 | 具体例・補足 |
|---|---|
| 未成年者 | 満18歳未満の人(2022年4月1日以降) |
| 推定相続人 | 遺言者の配偶者、子、親など、現時点で相続権を持つ可能性のある人 |
| 受遺者 | 遺言によって財産を受け取る人(相続人以外の場合) |
| 推定相続人および受遺者の配偶者 | 例:遺言者の子の配偶者(嫁・婿)、受遺者の夫・妻 |
| 推定相続人および受遺者の直系血族 | 例:遺言者の孫(推定相続人である子の子供)、受遺者の親・子 |
| 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記、雇人 | 公証役場関係者もなれません |
簡単に言うと、遺言の内容によって直接利害関係が生じる可能性のある人や、未成年者、公証役場の関係者は証人になれません。
【証人の探し方】
上記の欠格者に該当しない、信頼できる人であれば、友人、知人、会社の同僚などに依頼することも可能です。ただし、遺言というプライベートな内容を知られることになるため、依頼しにくい場合もあるでしょう。
そのような場合は、以下の方法があります。
- 行政書士、弁護士などの専門家に依頼する:守秘義務があり、経験も豊富なので安心です。遺言書作成の依頼と合わせて証人もお願いするのが一般的です。
- 公証役場で紹介してもらう:公証役場によっては、証人を紹介してくれる場合があります(紹介料や日当が必要な場合あり)。
- 信託銀行などに遺言信託を依頼し、担当者に証人になってもらう:遺言の保管や執行まで任せる場合に利用されます。
【証人への謝礼(日当)】
友人や知人に依頼する場合、謝礼は必須ではありませんが、お礼として1万円程度を渡すことが多いようです。専門家や公証役場紹介の証人に依頼する場合は、通常、1名あたり5,000円~15,000円程度の日当が必要となります(事務所や地域によって異なります)。
【注意点】
証人には、作成当日に公証役場に出向き、遺言者の口授を聞き、書面に署名・押印してもらう必要があります。事前に日程調整をしっかり行いましょう。また、証人にも守秘義務がありますが、依頼する相手は慎重に選ぶことが大切です。
💡ワンポイント
「身近に頼める人がいない」「遺言の内容を他人に知られたくない」というお悩みは非常に多く寄せられます。当事務所にご依頼いただければ、守秘義務を遵守し、公正証書遺言の証人経験が豊富なスタッフ、または提携する信頼できる専門家(他の行政書士など)を責任を持って手配いたします。証人探しに関するご心配は一切不要です。お客様のプライバシーを守りながら、安心して公正証書遺言を作成できる環境をご提供します。
問い合わせ先(初回無料相談)
電話0463-57-8330
(平日9:00〜18:00)
料金表はこちら
公証人手数料と専門家報酬の目安
公正証書遺言の作成には、主に以下の費用がかかります。
- 公証人手数料:
公証役場に支払う手数料です。これは法律(公証人手数料令)で定められており、全国一律です。主な内訳は以下の通りです。- 基本手数料:遺言書に記載される財産の価額に応じて計算されます。相続人・受遺者ごとに、受け取る財産の価額に対応する手数料を算出し、それらを合計します。 目的の価額(相続させる財産の価額) 手数料 100万円以下5,000円 100万円を超え200万円以下7,000円 200万円を超え500万円以下11,000円 500万円を超え1,000万円以下17,000円 1,000万円を超え3,000万円以下23,000円 3,000万円を超え5,000万円以下29,000円 5,000万円を超え1億円以下43,000円 1億円を超え3億円以下43,000円に超過額5,000万円までごとに13,000円を加算 3億円を超え10億円以下95,000円に超過額5,000万円までごとに11,000円を加算 10億円を超える場合249,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算
- 遺言加算:全体の財産額が1億円以下の場合は、上記基本手数料の合計額に11,000円が加算されます。
- 謄本代:遺言書の正本・謄本の作成費用として、通常1通あたり250円×枚数程度がかかります。
- その他:公証人が出張する場合は、基本手数料が1.5倍になり、日当(1日2万円、4時間まで1万円)と交通費が別途かかります。
妻分:29,000円、長男分:23,000円 → 基本手数料合計:52,000円
遺言加算:11,000円
合計:63,000円 + 謄本代など - 必要書類の取得費用(実費):
戸籍謄本(1通450円)、印鑑証明書(1通300円程度)、不動産の登記事項証明書(1通600円)、固定資産評価証明書(1通300円程度)など、書類を取得するための実費がかかります。通常、数千円程度です。 - 専門家(行政書士など)への依頼費用:
遺言書の原案作成、必要書類の収集代行、公証人との打ち合わせ調整、証人の手配、作成当日の同行などを依頼する場合の報酬です。依頼する業務範囲や財産額、内容の複雑さによって異なりますが、一般的に行政書士の場合、10万円~20万円程度が相場とされています。 - 証人への謝礼(日当):
前述の通り、専門家や公証役場紹介の証人に依頼する場合、1名あたり5,000円~15,000円程度の日当が別途必要になることがあります。
【費用の考え方】
公正証書遺言の作成には確かに費用がかかりますが、これは将来の安心への投資と考えることができます。もし遺言書がなく相続トラブルが発生した場合、弁護士費用などで何十万、何百万円もの費用がかかることも少なくありません。また、自筆証書遺言の検認手続きにも手間と時間がかかります。公正証書遺言を作成することで、これらのリスクや負担を回避できると考えれば、決して高い費用ではないと言えるでしょう。
💡ワンポイント
当事務所では、公正証書遺言作成サポートについて、分かりやすい料金体系を設定しております。初回のご相談(無料)の際に、お客様の状況をお伺いした上で、総額でどれくらいの費用がかかるのか、詳細なお見積もりを必ずご提示いたします。ご不明な点があれば丁寧にご説明し、ご納得いただいてから正式にご依頼いただく流れとなりますので、後から想定外の費用が発生することはありません。ご依頼いただく業務範囲(例:書類収集は自分で行う、証人は自分で手配するなど)に応じて、柔軟に費用を調整することも可能です。費用に関するご不安も含め、まずはお気軽にご相談ください。
問い合わせ先(初回無料相談)
電話0463-57-8330
(平日9:00〜18:00)
料金表はこちら
公正証書遺言が無効になるケースと対策
せっかく作成した公正証書遺言も、一定の条件下では無効と判断される可能性があります。ここでは、どのような場合に無効となるのか、その原因と、有効性を確保するために作成時に注意すべきポイント、そして遺言作成と密接に関わる「遺留分」について解説します。
無効原因と有効性を確保するためのポイント
公正証書遺言は無効リスクが低いとはいえ、絶対に無効にならないわけではありません。後日、遺言の有効性が争われ、無効と判断される可能性のある主なケースは以下の通りです。
- 遺言者に遺言能力がなかった場合:
遺言をするには、遺言の内容やその結果を理解できる判断能力(遺言能力)が必要です。作成時に遺言者が重度の認知症や精神疾患などにより、遺言能力を欠いていたと判断されると、遺言は無効になります。公正証書遺言では公証人が遺言能力を確認しますが、後日、相続人から「作成当時は既に判断能力がなかった」と主張され、裁判で争われるケースがあります。
【対策】高齢の方や病気療養中の方が作成する場合は、事前に医師の診断書を取得しておく、作成時の様子を録音・録画しておく、遺言能力について慎重な判断ができる専門家(行政書士など)に相談する、といった対策が考えられます。 - 証人が欠格者だった場合:
前述した証人の欠格者(推定相続人、未成年者など)が証人として立ち会っていた場合、その遺言は無効になります。
【対策】証人を依頼する際は、欠格者に該当しないか事前にしっかり確認することが重要です。専門家に証人を依頼すれば、このリスクは回避できます。 - 遺言者が公証人に口授しなかった場合:
公正証書遺言は、遺言者が公証人に遺言の内容を口頭で伝える「口授」が要件とされています。例えば、遺言者が話すことができず、単に頷いただけの場合や、事前に作成された書面を読み上げただけの場合などは、口授の要件を満たさないとして無効になる可能性があります。
【対策】公証人は通常、口授の要件を満たすよう手続きを進めますが、遺言者の意思表示が明確に行われたことを記録しておく(議事録作成など)ことも有効です。 - 詐欺や強迫によって作成された場合:
相続人の誰かに騙されたり、脅されたりして、本意ではない内容の遺言書を作成させられた場合は、遺言を取り消すことができます(民法第96条)。ただし、詐欺や強迫があったことを証明するのは容易ではありません。
【対策】作成プロセスに専門家が関与し、遺言者が自由な意思で遺言していることを確認する状況を確保することが重要です。 - 内容が公序良俗に反する場合:
例えば、「愛人に全財産を相続させる」といった内容が、著しく社会的な妥当性を欠き、公序良俗に反すると判断された場合、その部分が無効になる可能性があります(民法第90条)。ただし、愛人への遺贈が常に無効になるわけではなく、個別の事情によって判断されます。
【対策】社会通念上、著しく不公平・不道徳とみなされる可能性のある内容については、作成前に専門家に相談し、法的なリスクを確認することが望ましいでしょう。
💡ワンポイント
公正証書遺言の有効性を後日争われないためには、作成段階での細心の注意が必要です。当事務所では、ご依頼いただいた際には、まずご本人の意思確認を最も重要視し、時間をかけて丁寧なヒアリングを行います。特にご高齢の方の場合、ご家族の同席を求める場合もありますが、最終的な意思決定は必ずご本人にしていただき、そのプロセスを記録に残すようにしています。必要に応じて、提携する医師の意見を参考にしたり、認知機能テストの結果を参考にしたりするなど、客観的な証拠に基づき遺言能力の確認を慎重に行います。また、最新の判例動向を常に把握するため、AIを活用した判例検索・分析システムも導入し、あらゆる角度から無効リスクを検討し、最大限排除するよう努めています。お客様の想いが確実に未来へ繋がるよう、万全の体制でサポートいたします。
問い合わせ先(初回無料相談)
電話0463-57-8330
(平日9:00〜18:00)
料金表はこちら
遺留分侵害額請求とは?遺言作成時に考慮すべき法的知識
遺言書を作成する際には、「遺留分(いりゅうぶん)」という制度について理解しておくことが非常に重要です。遺留分を無視した内容の遺言書は、後に相続トラブルの原因となる可能性があります。
【遺留分とは?】
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人(配偶者、子、親など)に法律上保障されている、最低限の遺産の取り分のことです。遺言書によって、特定の相続人に全財産を相続させたり、相続人以外の人に多くの財産を遺贈したりすることも可能ですが、それによって他の相続人の遺留分が侵害された場合、遺留分を侵害された相続人は、財産を多く受け取った人に対して、侵害された遺留分に相当する金銭の支払いを請求することができます。これを「遺留分侵害額請求」といいます(民法第1046条)。
【遺留分割合】
遺留分の割合は、誰が相続人になるかによって異なります。
- 相続人が配偶者と子の場合:総遺産の1/2 × 法定相続分
- 相続人が配偶者のみ、または子のみの場合:総遺産の1/2
- 相続人が配偶者と親の場合:総遺産の1/2 × 法定相続分
- 相続人が親のみの場合:総遺産の1/3
- 兄弟姉妹には遺留分はありません。
例えば、遺言者が妻と子2人に全財産1億円を残した場合、遺留分総額は1億円×1/2=5,000万円です。妻の遺留分は5,000万円×1/2=2,500万円、子1人あたりの遺留分は5,000万円×1/4=1,250万円となります。
【遺留分を侵害する遺言も有効だが…】
遺留分を侵害する内容の遺言書自体が無効になるわけではありません。しかし、相続開始後1年以内(または遺留分侵害を知った時から1年以内)に遺留分侵害額請求権が行使されると、遺言書通りに財産を受け取った人は、遺留分権利者に対して金銭を支払わなければならなくなります。これにより、遺言者の意図した財産承継が実現できなくなるだけでなく、相続人間での深刻なトラブルに発展する可能性があります。
【遺言作成時に遺留分を考慮する重要性】
遺言者の意思を尊重しつつ、将来のトラブルを避けるためには、遺言書を作成する段階で遺留分に配慮することが重要です。具体的な対策としては、以下のようなものが考えられます。
- 遺留分を侵害しない範囲で財産配分を考える。
- 遺留分を侵害する可能性がある場合は、その理由や想いを付言事項に記し、遺留分権利者の理解を求める。
- 遺留分相当額を現金で準備しておく、または生命保険金を活用して支払い資金を確保する。(生命保険金は原則として遺産分割の対象外となり、遺留分算定の基礎財産にも含まれません)
- 生前贈与を活用する。(ただし、相続開始前10年以内の贈与などは遺留分算定の基礎に含まれる場合があり注意が必要)
💡ワンポイント
遺留分の問題は非常にデリケートであり、専門的な知識が必要です。当事務所では、お客様の財産状況やご家族構成、そして何よりもお客様の「想い」を詳しくお伺いした上で、遺留分に配慮した遺言内容のご提案を行います。「特定の相続人に事業を継がせたい」「長年介護してくれた長男の嫁にも財産を残したい」といったご希望を実現しつつ、将来の紛争リスクを最小限に抑えるための具体的なアドバイスをいたします。必要に応じて、提携している税理士とも連携し、相続税対策も含めた総合的な視点から、最適な財産承継プランの策定をお手伝いします。遺留分に関するご懸念も、ぜひ私たちにご相談ください。
問い合わせ先(初回無料相談)
電話0463-57-8330
(平日9:00〜18:00)
料金表はこちら
公正証書遺言作成を専門家に依頼するメリット
公正証書遺言の作成はご自身でも進められますが、専門家である行政書士に依頼することで、多くのメリットが得られます。ここでは、行政書士に依頼する意義と、当事務所ならではの強みを活かしたサポート体制について詳しくご紹介します。
専門家依頼がおすすめな理由
公正証書遺言の作成を行政書士などの専門家に依頼することには、以下のような大きなメリットがあります。
- 時間と労力の節約:
公正証書遺言の作成には、遺言内容の検討、財産調査、複雑な戸籍謄本等の書類収集、公証人との打ち合わせ、証人の手配など、多くの時間と労力がかかります。専門家に依頼すれば、これらの煩雑な手続きの多くを代行してもらえるため、ご自身の負担を大幅に軽減できます。特に、お忙しい方や手続きに慣れていない方にとっては大きなメリットです。 - 法的に不備のない確実な遺言書の作成:
行政書士は、遺言・相続に関する法的な知識と実務経験が豊富です。遺言内容が法的に有効か、表現が曖昧でないか、後々トラブルの原因にならないかなど、専門家の視点からチェックし、不備のない確実な遺言書を作成することができます。自筆証書遺言はもちろん、公正証書遺言であっても、内容の解釈を巡って争いになる可能性はゼロではありません。専門家が関与することで、そのリスクを最小限に抑えられます。 - 相続全体を見据えたアドバイス:
単に遺言書を作成するだけでなく、相続税対策、二次相続(次の相続)の問題、遺留分への配慮、遺言執行者の選定など、相続全体を見据えた総合的なアドバイスを受けることができます。お客様の状況に合わせた最適な財産承継プランを一緒に考えることができます。 - 精神的な負担の軽減:
遺言書の作成は、ご自身の「死」と向き合う作業でもあり、精神的な負担を感じる方も少なくありません。また、家族関係や財産について他人に話すことに抵抗を感じる方もいらっしゃるでしょう。専門家は、お客様の気持ちに寄り添いながら、客観的かつ中立的な立場で話を聞き、精神的な負担を和らげながら手続きを進めるお手伝いをします。 - 中立的な立場からのサポート:
特定の相続人に有利な遺言を作成したい場合など、家族内では話しにくいこともあるかもしれません。行政書士は中立的な第三者として、お客様の意思を尊重しつつ、他の相続人への配慮も含めたバランスの取れた遺言内容を検討するサポートができます。
確かに専門家への依頼には費用がかかりますが、上記のようなメリットを考えれば、それは将来の安心と円満な相続を実現するための有効な投資と言えるでしょう。
💡ワンポイント
当事務所は、創業以来1000件を超えるご相談に対応してまいりました。この豊富な経験を通じて痛感しているのは、遺言書は単なる法律文書ではなく、遺言者の大切な「想い」を未来へ繋ぐメッセージであるということです。私たちは、単に書類を作成する代行業者ではなく、お客様一人ひとりのご家族構成、財産状況、そして何よりもその「想い」を丁寧にヒアリングし、それが最も良い形で実現できるような遺言書作成をサポートすることを使命と考えています。専門家に依頼することで得られる「確実性」と「安心感」は、何物にも代えがたい価値があると、多くのお客様に実感していただいています。
問い合わせ先(初回無料相談)
電話0463-57-8330
(平日9:00〜18:00)
料金表はこちら
やさしい行政書士事務所ならではのサポート体制
数ある専門家の中から、やさしい行政書士事務所を選んでいただくメリットは、単に手続きを代行するだけではない、お客様に寄り添った独自のサポート体制にあります。
1. 相談しやすい環境づくり:
- LINEでの気軽な問い合わせ・相談:「ちょっと聞きたいことがある」「いきなり電話は…」という方でも、LINEなら気軽にメッセージを送れます。友達追加で無料相談も可能です。
- 土日祝・夜間対応(事前予約制):平日はお仕事でお忙しい方でも、ご都合の良い時間にご相談いただけます。
- 訪問相談(出張相談):事務所までお越しいただくのが難しい場合でも、ご自宅やご指定の施設、病院などへこちらからお伺いします。
- わかりやすい説明:専門用語を避け、丁寧で分かりやすい言葉でご説明することを常に心がけています。
2. 専門性と多様なニーズへの対応力:
- 外国人の方へのサポート:代表行政書士は在留資格(ビザ)申請の専門家でもあります。国際結婚されている方、日本に永住されている方、海外に財産をお持ちの方など、外国人の方特有の相続・遺言に関するご相談にも、豊富な知識と経験で対応いたします。必要に応じて本国の書類取得サポートなども行います。
- 高齢者の方へのサポート:ご高齢の方にも安心してご相談いただけるよう、ゆっくり丁寧な対応を心がけています。また、遺言だけでなく、元気なうちから老後の備えをする「任意後見契約」のサポートも得意としており、遺言と組み合わせることで、より包括的な老後の安心設計をご提案できます。
- 経営者の方へのサポート:会社の株式や事業用資産の承継は、通常の相続とは異なる配慮が必要です。当事務所では、建設業許可や飲食業許可などの許認可申請、法人設立にも対応しており、事業承継を見据えた遺言作成や、関連する法的手続きをワンストップでサポートできます。代表は大手企業での経営戦略策定や新規事業立ち上げ支援の経験もあり、経営者の視点に立ったアドバイスが可能です。外国人雇用に関するご相談(就労ビザなど)も承ります。
3. 効率性と正確性の追求:
- AI技術の活用:最新の判例検索や関連法規のリサーチ、書類作成の一部においてAI技術を活用し、業務の効率化と正確性の向上を図っています。これにより、お客様へのスピーディーな対応と、より質の高いサービスの提供を目指しています。
💡ワンポイント
私たちは、お客様からご依頼いただく業務を、単なる手続きの代行作業とは考えていません。お客様一人ひとりの大切な人生に関わる仕事であるという責任感を持ち、その想いをしっかりと受け止め、法的な専門知識とこれまでの経験、そして最新の技術も活用しながら、最適な形で未来へ繋ぐお手伝いをしたいと考えています。
「迅速・正確・丁寧」はもちろんのこと、事務所名の通り、お客様にとって「やさしい」存在でありたい。それが私たちの変わらぬ想いです。公正証書遺言の作成を通じて、お客様の未来の安心を築くサポートができることを願っております。
問い合わせ先(初回無料相談)
電話0463-57-8330
(平日9:00〜18:00)
料金表はこちら
まとめ
公正証書遺言は、ご自身の意思を法的に保護し、大切なご家族へ確実に想いを伝えるための非常に有効な手段です。作成には手間や費用がかかる側面もありますが、その確実性や相続手続きの円滑化といったメリットは、将来の安心にとって大きな価値があります。
この記事では、公正証書遺言の基本から作成手順、費用、注意点、そして専門家である行政書士に依頼するメリットまでを解説してきました。特に、証人の手配や複雑な書類収集、公証人とのやり取りなど、ご自身で進めるには不安や負担が大きいと感じる部分も多いかもしれません。
そんな時は、相続・遺言の専門家である行政書士にご相談いただくことをお勧めします。専門家は、法的な知識はもちろん、多くの実務経験に基づき、お客様一人ひとりの状況に合わせた最適なアドバイスとサポートを提供できます。
「やさしい行政書士事務所」では、これまで1000件以上の相談実績に基づき、公正証書遺言の作成を力強くサポートしています。LINEでの気軽なご相談から、ご自宅や施設への訪問相談、土日祝・夜間の対応(要予約)まで、お客様のご都合に合わせた柔軟な対応が可能です。外国人の方の遺言作成、高齢者の方の任意後見契約との連携、経営者の方の事業承継対策など、幅広いニーズにお応えできる体制も整えています。
「何から始めればいいかわからない」「費用が心配」「証人が見つからない」など、どんな些細なことでも構いません。まずは、やさしい行政書士事務所の無料相談をご利用ください。お電話、メール、LINEでお気軽にお問い合わせいただければ、代表行政書士の宮本が、あなたの想いを形にするお手伝いをさせていただきます。未来の安心への第一歩を、私たちと一緒に踏み出しませんか。
【お問い合わせはこちら】
やさしい行政書士事務所
代表行政書士 宮本 雄介
所在地: 〒257-0003 神奈川県秦野市南矢名2123-1
電話番号: 0463-57-8330 (受付時間:平日9:00~18:00)
メール: info@yusukehoumu.com
ウェブサイト: https://yusukehoumu.com/
▼LINEでのお問い合わせも可能です!▼
LINEで無料相談を予約する
初回相談は無料です。オンライン相談、夜間・土日相談(要予約)、訪問相談も承ります。お気軽にご連絡ください。
<<<TOPページへ>>>
◆お問合せフォーム
お問い合わせ内容は、公開されません。
安心してご記入ください。