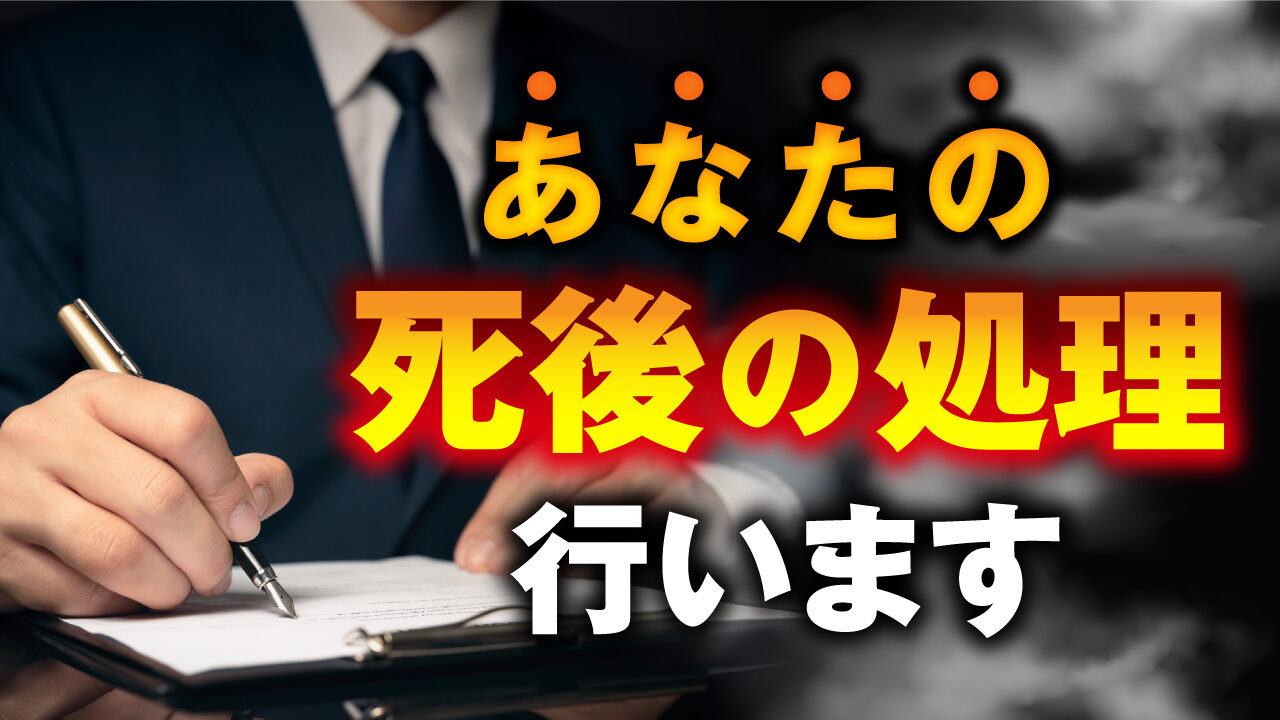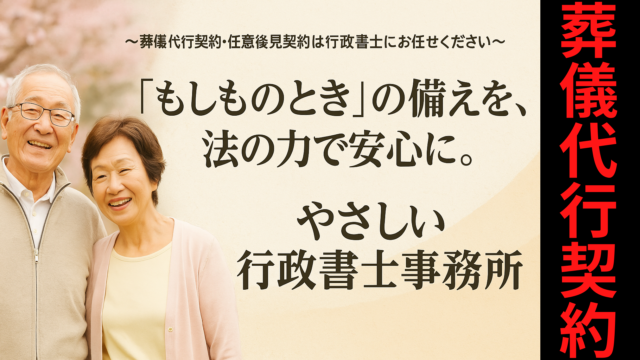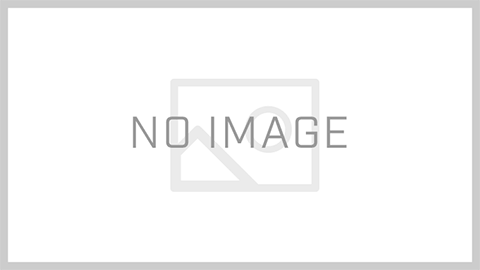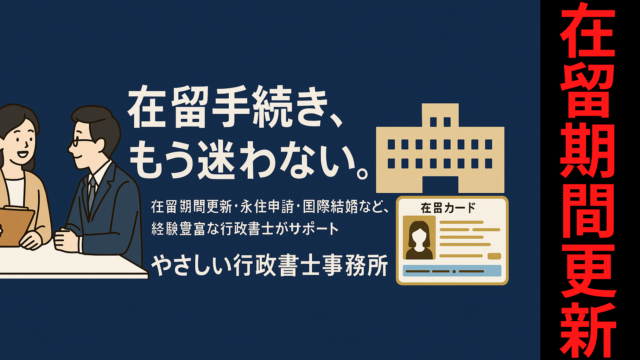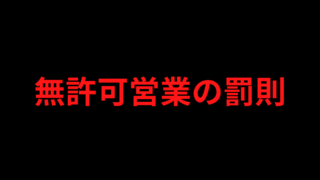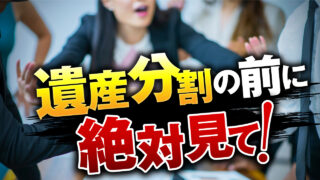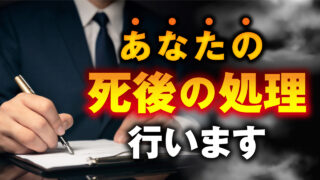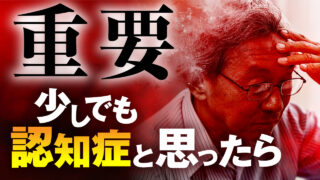「自分が亡くなった後、葬儀や手続きは誰がしてくれるんだろう?」
「家族に迷惑をかけたくない…」
「一人暮らしだから、もしもの時が心配」
そんな不安を抱えている方、実はとても多いんです。でも大丈夫!死後事務委任契約という制度を使えば、そんな心配も解決できるんですよ。
この記事では、死後事務委任契約について、専門知識がない方でも分かりやすく解説します。私たち「やさしい行政書士事務所」では、これまで1000件以上のご相談をお受けしてきました。その経験を踏まえて、あなたの不安を安心に変える方法をお伝えしますね。
目次
死後事務委任契約って何?簡単に説明します
死後事務委任契約とは、自分が亡くなった後に必要な手続きを、生きているうちに信頼できる人にお願いしておく契約のことです。
「でも普通、委任契約って本人が死んだら終わりじゃないの?」と思いますよね。確かにその通りなんですが、最高裁の判例で「死後の事務処理を頼むことは有効」とされているので、安心して利用できるんです。
死後事務委任契約と遺言書の違い
- 遺言書:「誰にどの財産を渡すか」を決める
- 死後事務委任契約:「死後の具体的な手続きを誰にやってもらうか」を決める
つまり、遺言書だけでは「お葬式や手続きを実際にやってくれる人」は決まらないんですね。だから、この二つはセットで考えるのがベストです。
💡 ワンポイントアドバイス
当事務所では、ご相談者様のお話をじっくり伺って、その方にとって最善の準備方法を一緒に考えています。まずは「どんなことが心配か」をお聞かせくださいね。
こんな方におすすめ!死後事務委任が必要なケース
死後事務委任契約は、どんな方に向いているのでしょうか?代表的なケースをご紹介しますね。
1. おひとり様・身寄りがない方
「自分の葬式、誰が出してくれるんだろう…」という不安、よく分かります。でも大丈夫!契約を結んでおけば、安心して毎日を過ごせるようになりますよ。
2. 家族が遠方・高齢・疎遠な方
子どもはいるけど遠くに住んでいる、子ども自身も高齢で大変そう…。そんな時も、第三者にお願いすることで解決できます。
3. 家族に負担をかけたくない方
これは本当に多いケースです。「大切な家族だからこそ、面倒をかけたくない」という優しい気持ち、とても素晴らしいと思います。
4. 内縁のパートナーや事実婚の方
法律上の結婚をしていないと、実は死後の手続きをする権限がないんです。長年連れ添ったパートナーに託したい場合は、ぜひ検討してくださいね。
5. 自分の希望を確実に叶えたい方
「葬儀は質素に」「お墓は海に散骨して」など、明確な希望がある方も多いですよね。契約書にきちんと書いておけば、確実に実現できます。
外国籍の方も安心してご相談を
当事務所は外国人の在留資格申請も専門としているので、外国籍の方特有の手続き(本国への連絡、領事館手続き、遺骨の送還など)についても詳しくサポートできます。日本語に不安がある方も、丁寧に対応させていただきますよ。
死後事務委任でお願いできる11のこと
では、具体的にどんなことをお願いできるのでしょうか?主なものを分かりやすくご紹介しますね。
| カテゴリー | 依頼できることの例 | 補足 |
|---|---|---|
| ① 死亡直後の対応 | ・亡くなった後の現場へのかけつけ ・医療機関等からの遺体引取り ・死亡診断書(死体検案書)の受領 ・親族、友人、勤務先等への連絡 | 誰に連絡してほしいか、連絡先リストを事前に準備しておくとスムーズです。電話での安否確認サービスも月5000円で行っております。 |
| ② 行政手続き | ・死亡届、埋火葬許可申請 ・年金受給停止手続き、未支給年金請求 ・健康保険、介護保険の資格喪失届 ・住民票の抹消届、世帯主変更届 ・運転免許証、パスポートの返納 | 期限のある手続きも多いため、迅速な対応が求められます。 |
| ③ 葬儀・供養関係 | ・生前の希望に沿った葬儀・火葬の手配、実行 ・菩提寺等への連絡、調整 ・納骨、埋葬に関する手配、実行 ・永代供養の手続き | 希望する葬儀形式、宗派、埋葬場所などを具体的に定めておきます。例えば成年後見だと、お坊さんを呼んでセレモニーとしての葬儀ができなくて火葬のみの直葬とか埋葬とかになってしまいます。それも家庭裁判所の許可や、その他一定の要件を満たす必要があります。死後事務委任だとセレモニーとしての葬儀も行うことができます。 |
| ④ 墓じまい | ・納骨または散骨の施行や先祖代々の墓じまい(改葬) | 最近では墓じまいして、自身の遺骨も海洋散骨される方も増えております。 |
| ⑤ 支払い・清算関係 | ・入院費、医療費の支払い ・老人ホーム等の施設利用料の支払い ・未納の税金、公共料金等の支払い | 支払いのための原資(預託金や遺産)について、別途取り決めておく必要があります。確定申告が必要な場合、事前に税理士の先生を紹介してます。 |
| ⑥ 退職手続き | 勤務先企業(機関) の退職手続き | 亡くなった時にまだどちらかに雇用されている場合、退職手続きを代行します。 |
| ⑦ 契約解除・解約関係 | ・公共料金(電気・ガス・水道) ・電話、携帯電話、インターネットプロバイダ ・クレジットカード、各種ローン ・新聞、定期購読サービス ・賃貸借契約(住居、駐車場等) | 解約に伴う精算手続きも含まれます。ちなみに郵便物の関係で、亡くなった後で、誰も住人が居なくても2、3か月ほどはキープすることをおすすめしてます。今、現状だと遺族の方にご本人宛の郵便転送とかができないんです。。。 |
| ⑧ 住居・遺品整理関係 | ・賃貸物件の原状回復、明け渡し ・家財道具、遺品の整理、処分 ・形見分けの手配 | 遺品整理業者への依頼や、処分方法について具体的に指示できます。個人情報が入ったPCとかスマホとか、見られたくないものについてはハードディスクを分解して壊したり、個別に業者に依頼して誰にも見られないようにして壊すこともできます。 |
| ⑨ デジタル遺品関係 | ・パソコン、スマートフォンのデータ処理 ・SNSアカウント、ブログ等の閉鎖、削除 ・ネットバンク、オンラインサービスの解約 | IDとパスワードを先にお伝えいただき、こちらでログインして削除します。ご希望があれば削除前の訃報の投稿も致します。 |
| ⑩ ペット関係 | ・ペットの一時保護、飼育 ・新しい飼い主探し、引き渡し ・終身飼育施設・ペット関連施設への入所手続き | 飼っているペットがいた場合、代わりに里親を探したり、希望の施設へ引き渡すこともできます。大型犬だと 受け入れができないなんて施設もあるので、事前の問い合わせが必要です。 |
| ⑪ 事務報告 | ・委任された事務の処理経過・結果の報告 ・費用に関する収支報告 | 通常、相続人に対して報告義務があります(民法645条)。報告先を指定することも可能です。 |
死後事務委任契約で依頼できる内容は多岐にわたりますが、一般的に以下のような項目が含まれます。これらを基に、ご自身の希望に合わせて内容を具体的に決めていきます。
特に注目!デジタル遺品の処理
最近特に問題になっているのが、パソコンやスマホの中のデータ。見られたくない写真や情報がある方も多いですよね。
当事務所では、事前にIDとパスワードをお預かりして、ご希望に応じて:
- 個人情報の完全削除
- SNSでの訃報投稿(ご希望があれば)
- ハードディスクの物理的な破壊
なども対応可能です。プライバシーは絶対に守りますので、ご安心くださいね。
お願いできないこともあります
これらはお願いできません:
でも大丈夫!これらが必要な場合は、任意後見契約や遺言書と組み合わせることで解決できます。
誰にお願いする?依頼先の選び方
死後事務委任の依頼先には、いくつかの選択肢があります。それぞれのメリット・デメリットを見てみましょう。
家族・親族にお願いする場合
メリット: 心情的な安心感、費用が安い
デメリット: 精神的・時間的負担が大きい、専門知識が不足
友人・知人にお願いする場合
メリット: 信頼関係がある、自分の気持ちを理解してくれる
デメリット: 責任が重すぎる、専門知識が不足、金銭トラブルのリスク
専門家(行政書士など)にお願いする場合
メリット: 専門知識と経験が豊富、客観的で公正、守秘義務あり
デメリット: 費用がかかる、相性が合わない場合がある
法人・団体にお願いする場合
メリット: 組織として継続性がある
デメリット: 費用が高額、サービスが画一的
💡 当事務所に依頼するメリット
行政書士は「契約書作成のプロ」です。また、当事務所では:
- 建設業や飲食業の許認可にも詳しいので、
個人事業主の方の複雑な手続きにも対応可能 - 夜間・土日相談、訪問相談、LINEでの相談も可能
- AI活用で効率化しつつ、人との対話を最も大切にしています
- 初回相談は無料です!
気になる費用の話
「いくらかかるの?」というのは、誰もが気になるところですよね。費用は大きく2つに分かれます。
1. 契約を結ぶ時の費用
- 行政書士への報酬相場: 5万円〜30万円程度
- 公正証書作成費用: 1万1千円〜数万円程度
2. 実際に死後事務を行う時の費用
- 実費(葬儀代、遺品整理代など): 数十万円〜数百万円
- 専門家への執行報酬相場: 20万円〜100万円以上
「えっ、こんなにかかるの?」と思われるかもしれませんが、これらの費用は事前にきちんと見積もりを出します。そして、準備する方法もいくつかあるんです。
費用の準備方法
- 預託金方式: 事前にまとまったお金を預ける(最も一般的)
- 生命保険の活用: 保険金を費用に充てる
- 遺言書での指定: 「費用は遺産から支払う」と遺言書に書く
- 信託の活用: 信託銀行のサービスを利用(最も安全)
💡 費用について当事務所の考え
当事務所では、費用の透明性を最も重視しています。契約前には必ず詳細な見積もりをお出しし、「なぜこの費用が必要なのか」を分かりやすくご説明します。納得いただけないまま進めることは絶対にありません!
契約の流れと注意点
実際に契約を結ぶ流れを、簡単にご紹介しますね。
契約までの8つのステップ
- 相談・ヒアリング → まずは不安や希望をお聞かせください
- 内容の決定 → 何をお願いしたいかを具体的に決めます
- 依頼相手の決定 → 誰に託すかを決めます
- 契約書案の作成 → 専門家が契約書を作ります
- 内容確認 → 契約書をしっかりチェックします
- 公正証書作成準備 → より確実にするため公正証書にします
- 公証役場で契約 → 正式に契約を結びます
- 費用の準備 → 預託金などを準備します
契約時に気をつけるべきこと
💡 当事務所のサポート
これらの面倒な手続きは、ほとんど当事務所で代行できます。必要書類の収集、公証役場との調整、契約書の作成など、お任せください。もちろん、各段階で丁寧にご説明しますので、安心してお進みいただけますよ。
さらに安心!遺言書・任意後見契約との組み合わせ
死後事務委任契約だけでも十分ですが、他の制度と組み合わせることで、より完璧な備えができるんです。
遺言書との組み合わせ
なぜ必要?
死後事務委任契約では「誰に財産を渡すか」は決められません。それは遺言書の仕事なんです。
組み合わせのメリット:
- 「死後事務の費用は遺産から支払う」と遺言書に書ける
- 同じ人を「遺言執行者」と「死後事務受任者」にできる
- 手続きがスムーズに進む
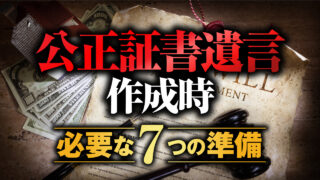
任意後見契約との組み合わせ
任意後見契約とは?
認知症などで判断能力が低下した時のために、元気なうちに後見人を選んでおく契約です。
組み合わせのメリット:
- 生前の判断能力低下から死後まで、同じ人にサポートしてもらえる
- 財産状況を把握しているので、死後事務がスムーズ
- 切れ目のない安心が得られる
| 制度名 | いつから有効? | 何をしてくれる? |
|---|---|---|
| 見守り契約 | 契約後すぐ | 定期的な安否確認 |
| 財産管理委任契約 | 契約後すぐ | 元気な時の財産管理代行 |
| 任意後見契約 | 判断能力低下後 | 財産管理・身の回りの世話 |
| 死後事務委任契約 | 亡くなった後 | 葬儀・各種手続き |
| 遺言書 | 亡くなった後 | 財産の分け方を指定 |
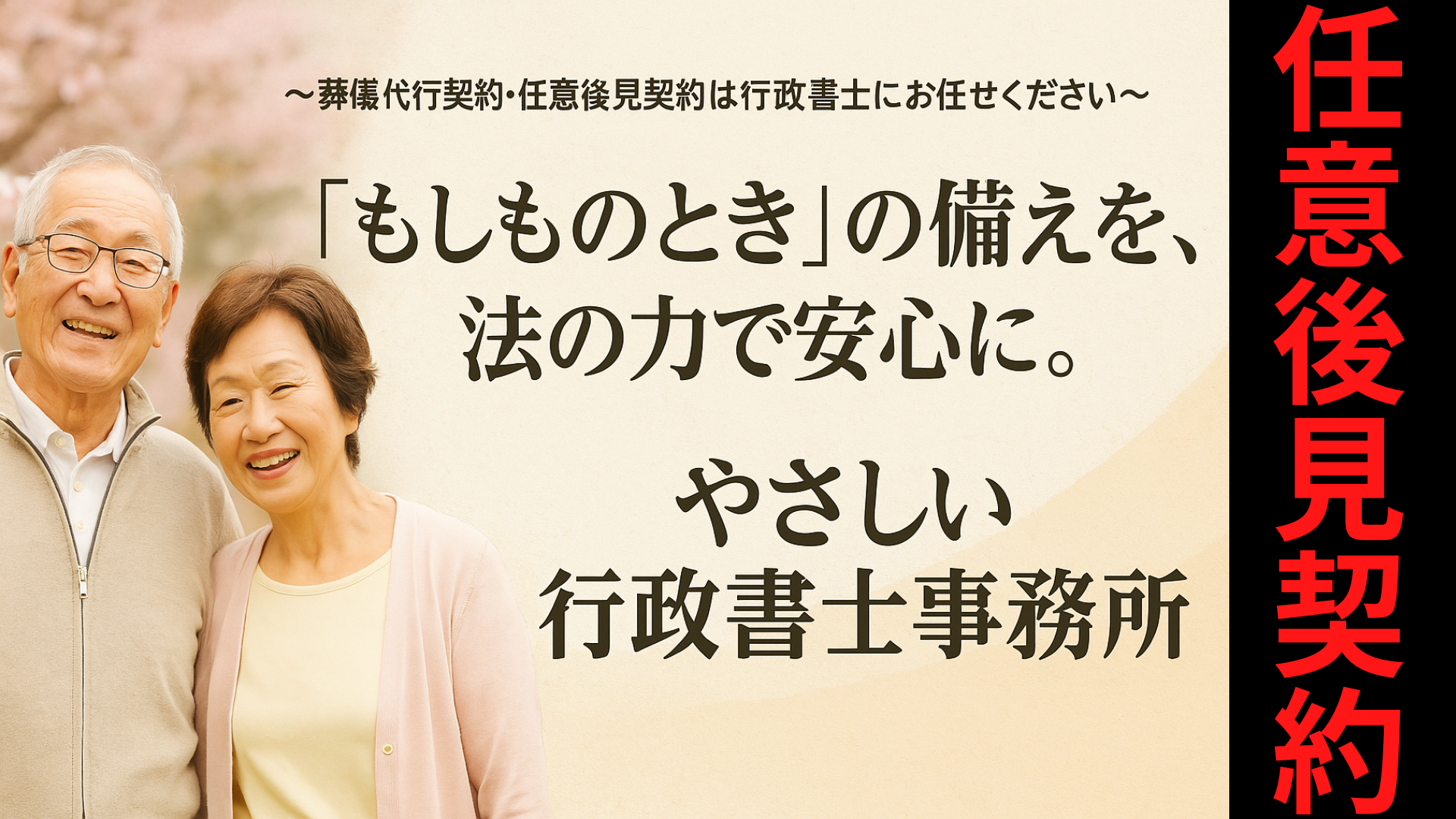
💡 当事務所の包括サポート
当事務所では、これら全ての契約書作成をサポートできます。お一人おひとりの状況に合わせて、最適な「安心プラン」をご提案しますので、ぜひご相談くださいね。
まとめ:一人で悩まず、まずは相談を
いかがでしたか?死後事務委任契約について、少しでも「なるほど、そういうことか」と思っていただけたでしょうか。
「手続きが複雑そう…」「誰に相談したらいいか分からない…」そんな不安を抱える必要はありません。
死後事務委任契約は、決して後ろ向きな準備ではありません。
ご自身の人生の締めくくりを自分らしく迎え、残される方への思いやりを形にする、とても前向きな終活の一つなんです。
私たち「やさしい行政書士事務所」は、これまで1000件以上のご相談をお受けしてきました。お一人おひとりの状況や気持ちに寄り添い、最適な解決策を一緒に考えます。
あなたの「もしもの時の不安」を「確かな安心」に変えるお手伝いをさせてください。まずはお気軽にご連絡くださいね。
【お問い合わせはこちら】
やさしい行政書士事務所
代表行政書士 宮本 雄介
所在地: 〒257-0003 神奈川県秦野市南矢名2123-1
電話番号: 0463-57-8330 (受付時間:平日9:00~18:00)
メール: info@yusukehoumu.com
ウェブサイト: https://yusukehoumu.com/
▼LINEでのお問い合わせも可能です!▼
LINEで無料相談を予約する
初回相談は無料です。オンライン相談、夜間・土日相談(要予約)、訪問相談も承ります。お気軽にご連絡ください。
<<<TOPページへ>>>
◆お問合せフォーム
お問い合わせ内容は、公開されません。
安心してご記入ください。